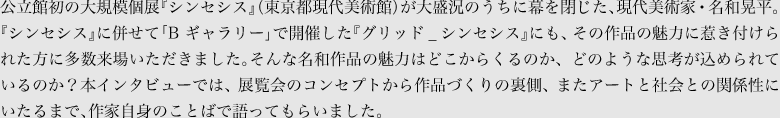

Q. 個展のタイトルについて、『シンセシス』と名付けた理由やコンセプトがあればお聞かせください。
2010年9月のSCAI THE BATHHOUSEでの個展で、同じポーズ、同じサイズの鹿の剥製を2体重ねて、それにビーズを貼って「PixCell-Double Deer」という作品を作りました。鹿の剥製を重ねるという事自体が乱暴な事をやっているのですけれど、存在としての鹿をイメージや情報として扱うことで新しい彫刻の領域に入るような手応えがあったことがきっかけです。(註:このSCAI THE BATHHOUSEでの個展は『Synthesis』というタイトルで開催された。)
シンセシスというのは、化学用語で「合成」、哲学用語では「総合・統合」という意味。自分が表現する彫刻やドローイングの世界、それらを連続した空間に並べて、全体をひとつの世界観として総合することが出来ないかという意味で『シンセシス』というタイトルにしました。
Q. アプローチの異なる各々の作品に、ひとつの統一したテーマや一貫したコンセプトはありますか?
作家活動が11年目になりますが、そのベースに流れているコンセプトといえば「Cell(セル)」という概念でしょうか。細胞、器、粒という意味のそれは、彫刻を作る方法論でもあり、展開される概念でもあります。今回の個展もまさに「セル」という概念がひとつのループの中で展開されています。ビームスの方に持って来たのは「グリッド」というシリーズです。グリッド(格子)という意味に加えて、格子の中のひとつひとつがセルだという捉え方も出来ます。
Q. 「セル」の概念や考え方の代表的な作品が、ビーズを使った「PixCell」シリーズだと思うのですが、
その成り立ちや製作背景を踏まえて、もう少し作品の意図するところを詳しく教えてください。
BEADSのシリーズ(註:「PixCell」シリーズのひとつ)はインターネットを使って収集したオブジェの表面をクリスタルガラスのビーズで覆います。覆う事で表面をレンズを通して見る事になると同時に、無数の球体で表皮が解体される。PCモニターの解像度を表すPixel(ピクセル・画素)に細胞のセルを合わせて「PixCell」という彫刻のフォーマットを作りました。ネットオークションでキーワードを設定して、検索でヒットしたものをたよりにモチーフを選んできました。
Q. インターネットもそうですが、世の中が便利になると色々と麻痺していきます。便利になることで
人が考えなくなったり、感じなくて済むようになって鈍化していくことをどう捉えていますか?
今は、麻痺したり鈍化したりすること自体はあまり肯定も否定もするつもりはありません。時代によって麻痺する部分、頻繁に使う部分、ある感覚に特化していくという事があるだろうし。むしろ、例えば「動物の剥製」を作ってしまう人間の感性の本質ってなんだろうと考えたり、あるいはとにかくデジタル化しないと落ち着かない、みたいな感覚。単なる社会の動向や目新しい文明の利器としてではなく、人間が開発する技術やシステム、それによって発生する新しい世界との関わり方やその状況が自らの身体、感覚、思考に与える影響に興味があるんです。
Q. それは、何かを「保存する」という感覚も含めてですか?
そうですね。
Q. 剥製も、デジタルデータもそうですが、基本的には「保存する」ことですよね。
昔はその方法がなかったから、例えば人の記憶の中、あるいは文字がない頃の言葉による伝承という
時間帯が長く続いた後、今のような状況になっています。
図録にも書きましたが、基本的には現実感というのは、固定出来ないと思うんです。それは常に動いているもので、人間の感覚や記憶、今感じていることは常にアクチュアルな状態。何も固定出来ないし、固定されているように見えることも、実は動いている。ただ、何もかもが動いていたり宙に浮いていたら不安なので、固定したいという欲求が働く。そこで、さまざまな表現メディアが必要に応じて生まれたんだと思います。目に見えるもの、あるいは夢で見たものを誰かに伝えるために絵が生まれたし、言葉を残すために文字が生まれた。
さらに詩や小説というパッケージへと進化する。写真や映像もそうですよね。よりリアルに、そのまま伝えたい、という意味で。絵画や彫刻も、心の中を表現したり、言葉にならない何かを伝える為に残されてきたのだと思います。
そういった造形表現の多くは外界あるいは内界を対象にしながら、キャプチャー(捕獲)、フィックス(固定)、エディット(編集)といった基本な動作から生み出されています。動物の剥製も動いているものを固定するという、非常にシンプルなフォーマット化が行われています。しかしそれは動物を撮影した写真や映像とは違う、物体です。しかも表面だけがリアルで、中身は空洞か、うつろな素材で出来ている。この構造がとても気になるんです。つまり、よくできた剥製は写真に撮った時、生きているかどうか判別しづらい。表層だけが(リアルに見える)イメージに覆われた薄っぺらな存在、それは剥製だけではないでしょう。
PixCellという彫刻には、そのようなリアリティへの問題意識、そして既存のフォーマットへのリアクションが込められています。

Q. デジタル画像もドットの集合体で出来上がっていますね。そういう事もある程度同義なのでしょうか?
そうですね。結局「セル」に戻るんですけど、いろんな感覚を紐解いていくと、結局は人間の身体のどこかに感覚する場所があって、そこに感覚細胞がグリッド状に並んでいる。ある刺激に対して反応が起こり、脳に伝わり、快・不快という反応が即座に起こる。つまり、どんな時代であれ、人間のコミュニケーションは、表皮から表皮へという構図で行われている。ある人の表皮で確認されたものが、別の人の表皮に伝わる。そう考えたらやっぱり「セル」っていうのは外せなくなってしまって。それをベースに、彫刻でもドローイングでも映像でも作っていくと、人の感覚に接続され易くなる。親和性が高い。また、一度接続すると次はより接続され易くなる。

『ドットシンセシス』という、絵の具の滴だけで描くドローイングをSCAIで発表した時に、10mmピッチで絵の具の滴を落とすという、ものすごいストイックなドローイングを二ヶ月間してました。毎日、毎朝……(笑)。ストイックすぎて頭がおかしくなったんですけど。最初は、普通にメモリを見ながらやるとずれるから網を敷いて、グリッドの網を敷いた間に、網に触れないようにドットを置いていました。ただの紙に滴を置くだけなのに、奥行きやレイヤー感など、視覚に対して妙に接続してくる感覚があって、身体の中の体験を外に持っていかれるみたいな手応えがあった。ある時絵の具をバシャってこぼしてしまって、網の下に入り込んだまま、それを放っておいたんです。それで、次の日見たらその網の下の絵の具の形がすごく立体感があって綺麗だったんですね。この失敗が今回の「グリッド」シリーズへとつながりました。(Pt.2へ続く)
