a fashion odyssey | 鶴田啓の視点
センスの所在
"MR_BEAMS"とは、ファッションをきちんと理解しながらも、
自分の価値観で服を選べる
"スタイルをもった人"のこと。
と同時に、決して独りよがりではなく、
周りのみんなからも「ステキですね」と思われる、
そのスタイルに"ポジティブなマインドがこもった人"のこと。
今回立ち上げたオウンドメディア#MR_BEAMSには、
私たちビームスが考える理想の大人の男性像と、
そんな理想の彼が着ているであろうステキな服、
そしてMR_BEAMSになるために必要な
洋服にまつわるポジティブな情報がギュッと詰め込まれています。
本メディアを通じて、服の魅力に触れていただいた皆様に、
ステキで明るい未来が訪れますように……。

a fashion odyssey | 鶴田啓の視点
先日、俳優の田村正和氏が亡くなった。
うちの父親世代(1940年代生まれ)からは「眠狂四郎」として、僕らの世代からは「古畑任三郎」として知られていた。僕よりも少し年上の先輩からすると「ニューヨーク恋物語」や「パパはニュースキャスター」なのかもしれない。氏が醸し出す独特のオーラはテレビの画面越しでもお茶の間にまではっきりと届いていたので、子供心には強く印象に残る存在だった。結果として、しばしば物真似の対象にもなっていたが、それほどオリジナルな個性の持ち主だったということでもある。
例えば、ドラマ「古畑任三郎」の中でも、田村正和氏は非常に個性的な刑事として事件現場に登場する。スーツにネクタイ姿の刑事や制服姿の警官など、「ごく一般的なステレオタイプの刑事像」に混じりながら、古畑任三郎はゆったりとしたコンチネンタルスタイルの黒っぽいスーツ+ノータイという出で立ちだ。劇中で「私はノータイで通している」と古畑本人が発言しているとおり、彼は昔からそういう主義(あくまでもキャラクター設定として)らしい。そして、ここで古畑が言う「ノータイ」の意味は「襟羽根のないスタンドカラーシャツを着る」ことを指す。警察のドレスコードがどこまで厳しいのかは正直知らないが、古畑以外の警官・刑事たちを見る限り、この作品の脚本や演出を手掛けた三谷幸喜や河野圭太は「服装に強いこだわりを持つお洒落な刑事」として古畑任三郎を描きたかったに違いない。
そして、法の番人としての厳粛さ・規律正しさが求められる警察において「お洒落である」ということは「アウトロー(はみ出し者)である」ことと同義である。特に日本の刑事ドラマには昔から泥臭いド根性モノが多く、「足で稼ぐ聞き込み調査」や「現場百篇」が基本であった。身なりに構っているヒマなどあるなら、容疑者全員のアリバイをもう一度洗いなおしてこい!な世界観。古畑のように全身を黒で固めた優雅なスーツスタイルでゆったりと自転車を漕ぎながら、遅れて現場にやってくる刑事は存在しないはずである。ちなみに古畑が乗る自転車は、たしか日本(ブリヂストン)製の「セリーヌ」だったと記憶している。
さらにちなむと、古畑とはまったく逆の手法(=身なりに無頓着)で「アウトローな刑事」を演出したのが「刑事コロンボ」のピーター・フォークである。1968年から始まったこのTVドラマシリーズでは、社会的地位の高い医者や俳優、弁護士といった犯人たちが、この年代らしくワイドラペルのジャケットや剣先9.5cmくらいはありそうなネクタイに身を包んでいる。一方で、ゴージャスな70’sスタイルの犯人達と対決するコロンボはペラペラの黒いナロータイによれよれのレインコート。うだつの上がらない薄汚れた風体の、だらしない三流オジサン刑事…と見せかけて、実は猟犬よりも鋭い鼻とワニのような粘り強さを併せ持つ凄腕なのである。よれよれの中年刑事がシャープな観察眼と推理力を駆使しながらキラキラのエスタブリッシュメントを追い詰めていく様は、実に爽快であり、実にアメリカ的である。
結局何を言いたいのかというと。つまり、一昔前までビジネスマンや公務員の世界で「ネクタイをしない」や「ペラペラの細いネクタイをする」という行為は、そのまま「アウトロー宣言」を意味していた。ある種のサインでもあったのだ。しかし時代と共に、世界中で「ビジネスウェアの自由化」が進み、ネクタイの意味は「必需品」から「あってもなくてもよいもの」(ともすれば「ネクタイ禁止」の職場もあるという)へと大きく変遷しつつある。

少し話を戻そう。田村正和が演じる古畑任三郎がいつも着ていたスタンドカラーシャツ。このデザインのシャツは襟羽根が付いたものに比べると、ちょっとした「ヌケ感」が感じられるらしく、この数年でクラシック業界でも人気のアイテムになっている。デザインソースは台襟付きのヘンリーネックやデタッチャブルカラーの襟をはずした姿など、幾つか想像できるものがあるが、個人的にはスタンドカラーシャツと言えば1970年代に三宅一生氏らがメンズファッションに取り入れた「民族服」の要素が思い浮かぶ。同時にジャケットの下にスタンドカラーシャツを着るのは、やはり「イッセイ ミヤケ」を愛する建築家やアーティストなどクリエイティブな職種の人々、というイメージがある。これは毛沢東の立ち襟ジャケットに由来すると言われるマオカラージャケットと同様に、ドレスコードが厳しい超・一流の社交界でも通用するクリエイティブ専用ウェアのような意味である。一般の人がブラックタイで集まる場にも、マオカラージャケットやスタンドカラーシャツ姿で現れるアーティストたち。ボウタイもカマーバンドも身に付けていないが、彼ら自身が紛れもないアーティストであり、着ている服が「イッセイ ミヤケ」や「アルニス」など、アーティスト/クリエイター御用達ブランドのものであれば、そのまま通用してしまうような顔パスの世界。

つまり、古畑がスタンドカラーシャツを長年愛用し、ネクタイだらけの刑事達の中でノータイルックを通すことが出来たのは、これまでに「数々の難事件を明晰な頭脳で即座に解決してきた実績」がある故で、どんなに遅れて現場に出勤して来ようとも、捜査中にホテルのルームサービスで注文した明太子スパゲッティを優雅に食しようとも、その後かならず「瞬時に手がかりをキャッチして核心に迫ってくれる」という信頼(=ブランド性)を彼自身が担保していたからに他ない。「古畑さんなら、仕方ない」というこの感じは、凡人からすると非常に羨ましいブランド力である。
そうそう、キャラ立ち刑事(デカ)と言えばドラマ「太陽にほえろ」(1972-1986)を思い浮かべる読者も多いだろう。ボス(石原裕次郎)と山さん(露口茂)が束ねる七曲署(ななまがりしょ)の捜査一課には、これでもかと言うくらい個性豊かな刑事たちが続々と集まってくる。「七曲がり」どころか何十人もの曲者が揃うこの部署で、今も視聴者の印象に強く残っているのは「なんじゃこりゃ?!」の殉職シーンで有名な「ジーパン(松田優作)」だろうか。ジーパン刑事は、その名の通りブルージーンズを愛用する空手の達人。他にも、勝野洋が演じたテンガロンハットがトレードマークの刑事は「テキサス」。ショーケンこと萩原健一はマカロニウエスタン風のスリーピースを着ていたので「マカロニ」。英国製のタバコやスーツを愛する沖雅也は、イギリスかぶれで「スコッチ」。山下真二は「スニーカー」。思わず突っ込みたくなるほど、外見(主に衣服の特徴)をそのままストレートに表現したニックネームばかりである。名は体を表す。この先、更に仕事着のカジュアル化が進むと、あるいはネクタイを身に付けている人の方が職場でもすっかり珍しくなり、それでも好きで毎朝タイドアップで出かけていたら、いつの間にか「ネクタイ」なんてニックネームを付けられた、なんてこともあるかもしれない。
そういえば、今から20年以上も昔の話。新入社員だった僕は、短めに裾上げしたコットンスーツにジョン・スメドレーのニットポロ、白いソックスとローファーを合わせてよく着ていた。後に知ったが、当時の僕は別フロアの先輩女性社員たちから「白いソックスの子」と呼ばれていたらしい。白ソックス刑事の殉職シーンが果たしてどのようなものかは分からないが(笑)、それから20年が経ち僕はやっぱり白いソックスを企画・商品化したのである。
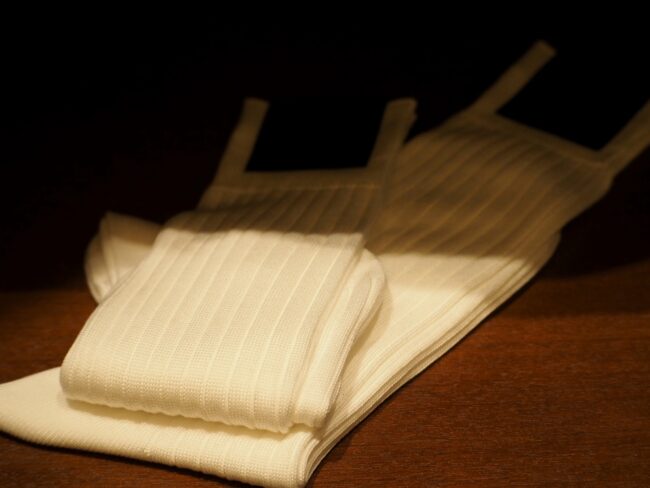
いまや白ソックスの洋服屋はそれほど珍しいものではないし、もはやスタンドカラーシャツを着たビジネスマンも普通に存在するだろう。服装のどの部分がその人を強く特徴づけるのか。それは時代に応じて変わりゆく。それでも、やはり身に付けるものは自分自身の生き方を表明するものであることに変わりはない。スタンドカラーシャツにコンチネンタルスーツ姿の古畑任三郎は難事件を華麗に解決しなければならないし、刑事コロンボはよれよれのコートで相手を油断させながらも、隙を見て犯人にガブリと噛みつかなければならない。仕事に責任を持つ一環として、服装にも責任を持つという事。もしも松田優作が危険な犯人を深追いせず、乱闘を避けながら会議室に閉じこもり、一張羅のジーンズを汚さないままで綺麗に殉職したのだとしたら、僕らはあのシーンに心を震わせなかったはずなのだ。
a fashion odyssey | 鶴田啓の視点
センスの所在
a fashion odyssey | 鶴田啓の視点
ロストバケーション②
a fashion odyssey | 鶴田啓の視点
ロストバケーション①