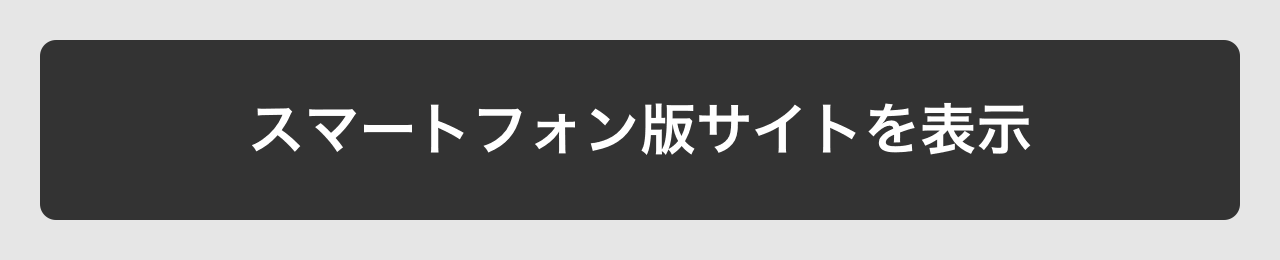※商品の色味は白背景商品単体で撮影した画像をご参照ください。
-
 -
-
-

-

-

-

-

-

桶栄 / 江戸結桶 片口
¥60,500(税込)
1,100ポイント付与
送料:330円

アイテム説明
和を演出、さまざまな用途で使える片口
1887年東京都深川にて創業、東京で唯一残る江戸結桶店〈桶栄(オケエイ)〉の片口。
水回りの器具や運搬、保存容器などに用いられた「結桶」の技術と清々しい香りの天然木「椹(さわら)」を使用して制作。
ほんのり爽やかな香りがして口当たりが優しい、口縁の片側に注ぎ口がついた器。酒器としてはもちろん、料理のを盛り付ける小鉢など自由にアレンジして楽しめます。
〈桶栄〉は、清々しい白木の側板を洋白銀の細「箍(たが)」で締めた江戸結桶の技術を用いて、品質と機能を守りながら、現代の生活様式にふさわしい姿と用途を追究し続けています。
【江戸結桶の工程】
・ぐるりに使う側板(がわいた)づくりが要となります。
・桶の高さに合わせて丸太を玉切りにし「くれ」または「くりしげ」と呼ばれる、への字型の鉈(なた)を当てて木槌で打ちつけ、柾目(まさめ)の割材をつくります。柾目取りするのは、材に狂いが出にくいからです。
・水分の少ない身の締まった内側の赤太(あかた)だけで製造。手割りした側板は水洗いと天日干しを繰り返しながら約半年かけて乾燥させ、さらに薪を焚いた室(むろ)で丸一日燻し乾燥します。
・手間も時間もかかる下準備ですが、こうしてアクや水分を抜き切ることで、木は引き締まり、粘りも出て、強度のある材になるのです。
【江戸結桶の素材】
木材部分:樹齢300年の木曽産天然 椹(さわら)。年輪が緻密で揃っているため収縮率が均等で狂いにくく、油分が多いことから水や酸に強いという利点があり、軽くて香りもやわらかい素材。
金属部分:洋白銀はジャーマンシルバーとも呼ばれ銅、ニッケル、亜鉛の合金です。時計やカトラリーに使用され、さびや変色になりにくく、強度がある素材。
【江戸結桶の特徴】
水回りの器具や運搬、保存、醸造などの容器に用いられてきた桶。 割板を丸や小判形に接合して竹や金属の細いコードである箍(たが)で固定し作られる。江戸結桶といえば質実ですっきりした形と材のほどよい厚みが特徴です。
【お手入れの方法】
・使う度に、水やぬるま湯で流してからお使い下さい。汚れやしずくの跡がつきにくくなります。
・へちまやふきんを使い、水やぬるま湯で洗って下さい。(洗剤は磨き粉、石けん等をお使い下さい。桶の金属タガ等のくもりも磨き粉で磨くともとにもどります。)
・乾いた布で水滴をふきとり風とおしの良い場所に横にころがして、影干しして下さい。
・一日(24時間)乾燥させて使用して下さい。(木の表面はすぐ乾きますが、内部は水を含んでいる場合があります。)
【注意事項】
・長時間、湯や水につけ置きしないで下さい。
・熱湯や食器洗浄機、電子レンジは使用しないで下さい。
・保管の際は、直射日光や極度の湿気、乾燥はさけて紙で包み箱などに入れるなどして収納下さい。
・保管状況によって、樹脂がにじみ出ることがあります。
・手作業で作られているため、一点一点風合いが若干異なります。
※撮影環境による光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境によって実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
※商品の色味は白背景商品単体で撮影した画像をご参照ください。
 ※〈ビームス ジャパン〉オリジナルラッピングサービスにつきまして
※〈ビームス ジャパン〉オリジナルラッピングサービスにつきまして
水回りの器具や運搬、保存容器などに用いられた「結桶」の技術と清々しい香りの天然木「椹(さわら)」を使用して制作。
ほんのり爽やかな香りがして口当たりが優しい、口縁の片側に注ぎ口がついた器。酒器としてはもちろん、料理のを盛り付ける小鉢など自由にアレンジして楽しめます。
〈桶栄〉は、清々しい白木の側板を洋白銀の細「箍(たが)」で締めた江戸結桶の技術を用いて、品質と機能を守りながら、現代の生活様式にふさわしい姿と用途を追究し続けています。
【江戸結桶の工程】
・ぐるりに使う側板(がわいた)づくりが要となります。
・桶の高さに合わせて丸太を玉切りにし「くれ」または「くりしげ」と呼ばれる、への字型の鉈(なた)を当てて木槌で打ちつけ、柾目(まさめ)の割材をつくります。柾目取りするのは、材に狂いが出にくいからです。
・水分の少ない身の締まった内側の赤太(あかた)だけで製造。手割りした側板は水洗いと天日干しを繰り返しながら約半年かけて乾燥させ、さらに薪を焚いた室(むろ)で丸一日燻し乾燥します。
・手間も時間もかかる下準備ですが、こうしてアクや水分を抜き切ることで、木は引き締まり、粘りも出て、強度のある材になるのです。
【江戸結桶の素材】
木材部分:樹齢300年の木曽産天然 椹(さわら)。年輪が緻密で揃っているため収縮率が均等で狂いにくく、油分が多いことから水や酸に強いという利点があり、軽くて香りもやわらかい素材。
金属部分:洋白銀はジャーマンシルバーとも呼ばれ銅、ニッケル、亜鉛の合金です。時計やカトラリーに使用され、さびや変色になりにくく、強度がある素材。
【江戸結桶の特徴】
水回りの器具や運搬、保存、醸造などの容器に用いられてきた桶。 割板を丸や小判形に接合して竹や金属の細いコードである箍(たが)で固定し作られる。江戸結桶といえば質実ですっきりした形と材のほどよい厚みが特徴です。
【お手入れの方法】
・使う度に、水やぬるま湯で流してからお使い下さい。汚れやしずくの跡がつきにくくなります。
・へちまやふきんを使い、水やぬるま湯で洗って下さい。(洗剤は磨き粉、石けん等をお使い下さい。桶の金属タガ等のくもりも磨き粉で磨くともとにもどります。)
・乾いた布で水滴をふきとり風とおしの良い場所に横にころがして、影干しして下さい。
・一日(24時間)乾燥させて使用して下さい。(木の表面はすぐ乾きますが、内部は水を含んでいる場合があります。)
【注意事項】
・長時間、湯や水につけ置きしないで下さい。
・熱湯や食器洗浄機、電子レンジは使用しないで下さい。
・保管の際は、直射日光や極度の湿気、乾燥はさけて紙で包み箱などに入れるなどして収納下さい。
・保管状況によって、樹脂がにじみ出ることがあります。
・手作業で作られているため、一点一点風合いが若干異なります。
※撮影環境による光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境によって実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
※商品の色味は白背景商品単体で撮影した画像をご参照ください。
 ※〈ビームス ジャパン〉オリジナルラッピングサービスにつきまして
※〈ビームス ジャパン〉オリジナルラッピングサービスにつきまして1887年創業、辰巳芸者で知られる深川の花街で、初代川又新右衛門の飯びつや桶が姿と仕事のよさで評判を呼びました。材料と需要に恵まれた土地で、職人が腕を磨き当時と変わることがない伝統の技を受け継ぎ、良質な材を選び抜いて、清々しい白木の結桶をつくり続けています。
店舗へのお問い合わせの際は下記品番をお伝え下さい。
商品番号:56-71-1011-444
アイテム詳細
| レーベル | : | BEAMS JAPAN |
| 性別 | : | MEN |
| カテゴリ | : | 食器・キッチン・食品 > グラス・マグカップ |
| サイズ | : | ONE SIZE |
| 素材 | : | 天然木(さわら)、洋白銀(ジャーマンシルバー) » 洗濯表示・お手入れについて |
| 原産国 | : | 日本製 |
| 商品番号 | : | 56-71-1011-444 |
| 返品 | : | 可能 |
| ギフトラッピング : 可能 »詳しくはこちら | ||
アイテムサイズ
| ONE SIZE | : | 直径 8.7/高さ 9.4 |
×
ご注文について
刺繍専用商品です。ご注文後、商品ページに設置の「オーダーフォーム」より、ご希望の刺繍文字を1週間以内にお知らせください。