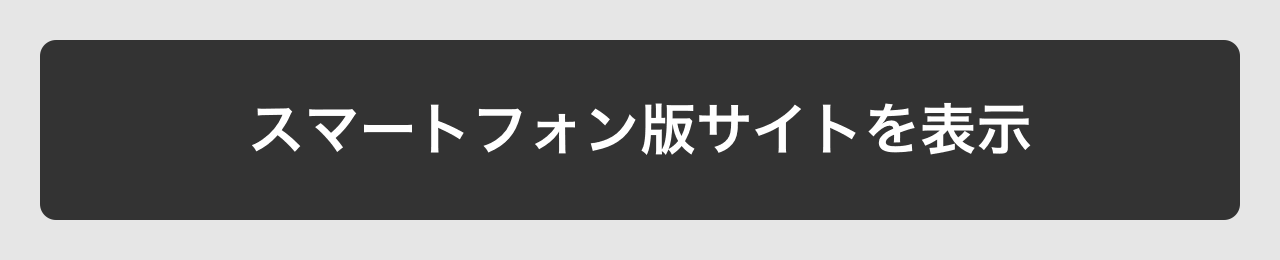※商品の色味は商品単体で撮影した画像をご参照ください。
-
 白
白
-
 青
青
-

-

-

-

-

-

-

-

-

小代焼 / 瑞穂窯 耳付鉢
¥5,500(税込)
100ポイント付与
送料:330円

アイテム説明
素朴で上品な佇まい
熊本県荒尾市〈小代瑞穂窯〉耳付き鉢。
古小代の技法をベースに独自の藍釉を取り入れ、伝統と革新が融合した器を生み出しています。
食卓に温もりと彩りを添える、素朴で上品な雰囲気が魅力です。
【陶器・磁器のご使用に関して】
●料理を盛り付けする前に水に通してから使うと匂いや油分が付きにくくなります。
●うつわを洗った後はよく乾燥させてから保管して下さい。
●染みや匂い移りが気になる場合は「目止め」も予防策の一つです。米のとぎ汁、または小麦粉や片栗粉を溶いた水とうつわを鍋に入れ、弱火で15~20分ほど煮沸したら火を止め、そのまま冷まします。その後は軽く洗いよく乾燥させて下さい。
●オーブン不可・電子レンジ、食洗機の使用はお勧めしておりません。
※光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境によって実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
※商品の色味は商品単体で撮影した画像をご参照ください。
瑞穂窯
民芸店を営んでいた福田豊水氏が、古小代を集めていた祖父の影響を受けて1973年に独学で開窯。2代目の福田るいさんは、大学で油絵を学んだ後、父・豊水氏の元で修行後、益子焼の島岡達三氏に師事し、帰郷して作陶を続けています。瑞穂窯は古小代の再現に取り組み、釉薬の研究に情熱を注ぎ小代焼の伝統である灰釉をベースとした釉薬を使用。釉薬の灰の元である藁や籾にもこだわりを持っています。昔ながらの特徴と技法を受け継ぎ活かしながら、独自の青「藍釉」や印花、鎬などの技法を取り入れ、和洋問わず現代の生活に合う器を作陶しています。
古小代の技法をベースに独自の藍釉を取り入れ、伝統と革新が融合した器を生み出しています。
食卓に温もりと彩りを添える、素朴で上品な雰囲気が魅力です。
【陶器・磁器のご使用に関して】
●料理を盛り付けする前に水に通してから使うと匂いや油分が付きにくくなります。
●うつわを洗った後はよく乾燥させてから保管して下さい。
●染みや匂い移りが気になる場合は「目止め」も予防策の一つです。米のとぎ汁、または小麦粉や片栗粉を溶いた水とうつわを鍋に入れ、弱火で15~20分ほど煮沸したら火を止め、そのまま冷まします。その後は軽く洗いよく乾燥させて下さい。
●オーブン不可・電子レンジ、食洗機の使用はお勧めしておりません。
※光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境によって実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
※商品の色味は商品単体で撮影した画像をご参照ください。
瑞穂窯
民芸店を営んでいた福田豊水氏が、古小代を集めていた祖父の影響を受けて1973年に独学で開窯。2代目の福田るいさんは、大学で油絵を学んだ後、父・豊水氏の元で修行後、益子焼の島岡達三氏に師事し、帰郷して作陶を続けています。瑞穂窯は古小代の再現に取り組み、釉薬の研究に情熱を注ぎ小代焼の伝統である灰釉をベースとした釉薬を使用。釉薬の灰の元である藁や籾にもこだわりを持っています。昔ながらの特徴と技法を受け継ぎ活かしながら、独自の青「藍釉」や印花、鎬などの技法を取り入れ、和洋問わず現代の生活に合う器を作陶しています。
小代焼とは約400年前に始まった熊本県を代表する焼き物です。技術・技法としては朝鮮半島の陶磁器の流れを汲んでいます。釉薬の深い美しさと自由奔放な流し掛けの模様は素朴な味わいが有り、ふだん使いのうつわとして暮らしの中で生きづき、その力強い作風は茶陶としても愛されています。深い藍と碧の地に白掛けが溶け込んだ釉薬が特徴の小代焼は、芸術品としての評価の高い焼き物です。
店舗へのお問い合わせの際は下記品番をお伝え下さい。
商品番号:56-71-1683-766
アイテム詳細
| レーベル | : | fennica |
| 性別 | : | MEN |
| カテゴリ | : | 食器・キッチン・食品 > 食器 |
| サイズ | : | ONE SIZE |
| 素材 | : | 陶器 » 洗濯表示・お手入れについて |
| 原産国 | : | 日本製 |
| 商品番号 | : | 56-71-1683-766 |
| 返品 | : | 可能 |
| ギフトラッピング : 可能 »詳しくはこちら | ||
アイテムサイズ
| ONE SIZE | : | 直径 14/高さ 4.7 |
×
ご注文について
刺繍専用商品です。ご注文後、商品ページに設置の「オーダーフォーム」より、ご希望の刺繍文字を1週間以内にお知らせください。