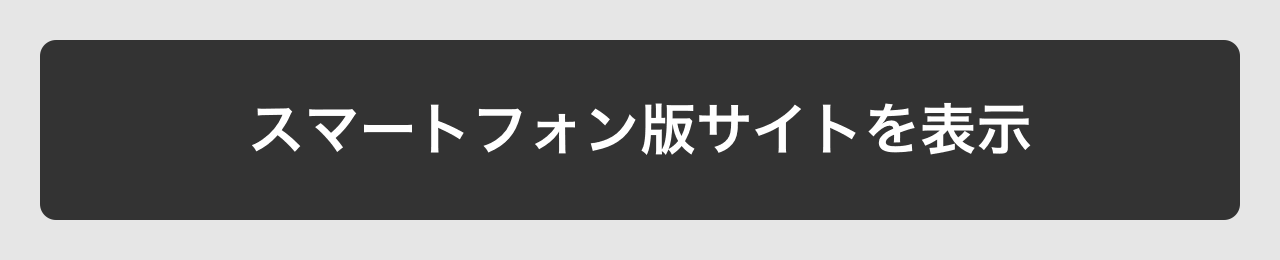みなさま初めまして。
EFFE BEAMSディレクターの安藤です。長らく、こちらのブログを放置してしまってすみません。。。
まず、EFFE BEAMSというレーベルのコトを少しだけ。
2002年、現在の「ビームス ハウス 丸の内」のオープンと共にスタートし、16年。初代のディレクターは、、、実は今、メンズドレスの統括のクリエイティブディレクターである、中村達也なんです。中村をご存知の方は、このことからも、なんとなーくお分かり頂けるかと思いますが、EFFE BEAMSでは、作り手とお客様の間に立ち、「そのモノ」の本当の良さを見つけるコト、作るコト、伝えるコトを、レーベル発足当時から、今なお大切にしています。これから改めて、EFFE BEAMSのコトを少しずつお伝えしていけたらなと思っておりますので、お時間ありますときに、のぞいて頂けたら嬉しいです。
「EFFE BEAMSのこと」
第1話は、大切に作り続けているオリジナルのお話し。EFFE BEAMSでは毎シーズン、インポートや国内の素敵な生地を使い、日本の職人さんの手によって丁寧に、素敵に仕上げてもらった、オリジナルのアイテムを展開しています。失われつつある、職人さんたちの卓越した技術。手でステッチを施したりして頂いているのですが、おじいちゃんおばあちゃんの職人さんもいらっしゃって、この美しい技術と精神がつまった商品が出来上がると、なんだか感慨深い気持ちになります。(いつまで縫ってくれるのかなぁ・・・と、生産担当の君塚もヒヤヒヤ)その中でも、シーズン問わず人気のアイテムが、フラワージャガードや、フラワープリントのスカートたちです。
まずはこちら↓

イタリア、BINDA社のシルクのプリント生地を使用したスカートです。
カジュアルな印象のニットから、流れ落ちるようなシルエットがとても美しく、動くたびにひらひらと、女性らしさを存分に楽しめるスカート。合わせるアイテムによっては、ドレスアップのシーンにも活躍します。またこちらは、わたくしが、今シーズン1番お気に入りで、全力でオススメしたいコーディネート。オーバーなシルエットのコーディネートは、バランスが難しいところですが、こちらは試行錯誤をし、大人の女性にこそ合わせて欲しい、絶妙なルーズなバランスに仕上げています。とてもステキなアランニットのお話はまた今度。
まったく印象の違う、プリント違いがこちら↓

より、女性らしいリッチな印象のスカートに仕上がっています。アランニットは、色違いでグレーもありますので、こちらのスカートにグレーを合わせるのも素敵ですよ。
もう一つご紹介したいスカートがこちら↓

こちらも、イタリアのGHIOLDI社に別注で作って頂いた素材を使用した、EFFE BEAMSには欠かせないシルエットのボリュームスカート。チュールに施されたブルーフラワーのジャガードが、とても華やかな1着です。ここで、なぜEFFE BEAMSがボリュームシルエットのスカートを提案し続けているのか。私なりの想いを少し。
1947年のパリ。戦後、まだまだ物資が不足していた時代、女性の洋服も地味な色とボックス型の洋服が主流でした。そんな中、Diorが発表した初のクチュールコレクションは、なめらかな肩のライン、協調されたバストライン、きゅっと絞られたウエストから、まるで花のように地面にむかって広がる、ひざ下丈のボリュームスカートが印象的な、女性らしさが最大に表現されたスタイルでした。コロール(花冠)・ラインと命名されたシルエットですが、当時、それをショー会場で見たハーパース・バザーの編集長カーメル・スノーが、「ニュールックだ」と絶賛したことで、今では「ニュールック」として知られる様になっています。当時の女性に衝撃をあたえたこのスタイルは、女性のスタイルを劇的に変えたのです。そして、70年経った今でも色あせる事なく、今なお世界中の女性に愛されています。抑圧された重い空気を、このスタイルが華やかな世界へと変えたのではないのか。当時の女性達が、このシルエットを見て、洋服に夢をみたのではないのか。ニュールックが、今でも女性の洋服に影響を与え続けていることは明かで、そんなニュールックに欠かせないのが、裾にむかって花の様に広がるボリュームスカートです。
EFFE BEAMSでは、時代を超えて愛されるモノを大切にしたい、70年経った今なお愛されている、この女性らしいスタイルを大切にしたいという想いから、シーズン問わず、エレガントなボリュームスカート提案し続けています。このブルーフラワーも、そんな想いを込めて作ったスカートです。当時の女性へ想いを馳せて、洋服をコーディネートするのも楽しいですよね。最初なので、すごく長くなってしまいました。最後まで、お読み頂きありがとうございます。そして、これからも。どうぞよろしくお願い致します。
Andy