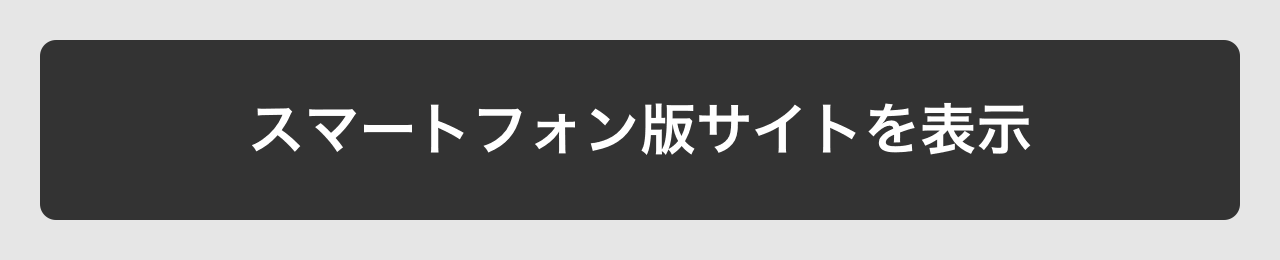山縣さんに聞きました「後半」編
商品について・日本の生地屋さんについてのお話です
(前半はこちらから)
今回 販売となるアイテムは
<writtenafterwards>2019AW・2020SSコレクションに登場していた2型を
今回限りの色・生地にのせ 同じアイテムでも全然違うようにみせる
そして ずっと手放せないような特別なものにしたい
1点1点 個性的で きらきらしたものが
お店に ずらーっと並んだら どんなにドキドキするだろうか
”可愛い””美しい”には 人の数 色々あってよく
サイズのコンプレックスも取り払いたい
そんな初めの気持ちに writtenafterwardsの皆様が共感し応えてくださった洋服なのです
さて 山縣さんからのお話です

●まずは今回 「wonsaponatime store」に並ぶ アイテムについて

『ニットボレロ』
このニットは島精機というホールガーメントの機械を発明した会社と協業で製作しました。
※ホールガーメント ・・・縫い目のない編み方のこと
通常は前見頃、後ろ見頃、袖など別々のパーツ編んでから、それぞれを縫い合わせて1着のニットを製作しますが、
この機械は1着のニットを丸ごと編み上げることができます。
別々のパーツを作って裁断して縫製するという工程がないため、無駄な糸を使用することがなく、作業工程も少ないのでとてもエコロジーです。
今回は「立体的に編み上げる」ことを生かしたデザインを目指しました。
この機械ならではの編み込みで、平たく置きたくても置けないほどの立体感を作り、ポンチョのように体を包み込みます。
袖はそのボリュームをつぶすことなく編まれており、縫代によるストレスは軽減され、利便性がプラスされています。
使用した糸はモール糸でベルベットのような効果を発揮し、光を吸収して奥深い色合いを表現できます。
この糸が立体的なニットの陰影を強調し、より立体的に見える表現を可能にしました。

『スモック』
インスピレーション源は古着のファーマーズスモックです。
スモックの歴史は古く、18世紀前半ころのイギリスが起源と言われています。
羊飼いや農業従事者、軽作業時に着用するワークウェアとして用いられていました。
なので、生地は肉厚のリネンや羊毛で作られ、丈は ももやふくらはぎまで長さがあり、
動きやすさのため脇下のマチやスモッキング刺繍、ギャザーによるボリュームというディテールがあります。
このスモックを現代的に解釈し、製作しました。

脇下のマチのディテールはそのままに。
袖、襟ぐりのギャザーはたっぷりと寄せ、丈は着やすく短めに、さらに裾、袖口にもギャザーを寄せふんわりとデザインしました。
また昔のスモックは制作された地域、着用者の職業によって刺繍の文様や様式が異なっており、地域に根付いた伝統がありました。
今回は、刺繍の代わりに、桐生のそれぞれの工房が培ってきた伝統的な文様の生地を使用しています。
●スモックに使用したビンテージ生地について
探していたときのエピソードや思い入れを教えてください
生地を探すにあたりアイテムのデザインに合うということも大切なポイントでした。
“特別な服を作りたい”という思いから、特別な素材を探すため、まだ寒い初春に私たちは日本の絹織物の中心的な役割を担っていた、
群馬県桐生産地に覗いました。桐生産地は明治時代に富岡製糸場が建設され、世界遺産にも登録された場所です。
日本の繊維産地は輸入生地の浸透により、絶滅の危機に瀕しています。
現在、生き残っているのは長年の国際競争の中を生き残ってきた工房で、非常に高い技術を有しています。
桐生で織物が始まった歴史はとても古く、奈良時代には朝廷に絹を献上した記録が残っています。
渡良瀬川と桐生川などの豊富な水資源を擁し、養蚕業に適した土壌を持っていました。
京都の西陣や西洋から積極的に技術を導入し、江戸時代には「西の西陣、東の桐生」と言われ西陣と肩を並べるほどの発展を遂げ、
伝統的な高級絹織物の産地となりました。
現在の桐生産地では、絹織物だけでなく、世界屈指の化合繊に関するニット・縫製・刺繍・染色整理業などの多様な生産拠点が点在しており、
化合繊のジャカード生地なども生産しています。
しかし、日本の繊維産業は世界的にも高度で繊細な伝統技術が有りながらも衰退の一途をたどっており、
桐生産地も例外ではなく、毎年のように工場の閉鎖の話を聞きます。
また、ファッション業界は、毎年過剰に洋服を供給しています。その分、廃棄されるものも多くあり、地球環境に与える影響は計り知れません。
伝統や職人は守りつつも、過剰な生産を減らしていくという課題にファッション産業は取り組まなければなりません。
これからの環境にどのように適応していくかというのは私たちのブランドにとっても大きな課題となっています。
今回のPOP-UPでは新しく生地を製作するのではなく、
生地工房で眠っているクオリティの高いアーカイブ生地に焦点を当て、眠っていた生地に命を宿すことにしました。
このアーカイブの生地を使用したスペシャルなピースを10点ご用意いたしました。
それぞれが職人が拘って製作した生地を使用しております。
ご協力頂いた桐生の3つの工房をご紹介いたします。
1.桐生絹織物株式会社
シルクを主原料とし突っ切りベルベット、幅の異なる縦サッカー、ホグシジャカード、ドビー、タフタ、ヘビーサテン等々、特殊織物を生産し、それらを高級毛皮用の裏地として北米、ヨーロッパに輸出することで事業を拡大しました。
現在はその蓄積した技術を活かし、婦人服地、フォーマル生地、ストール等、多種多様なテキスタイルを製作しています。高速量産では決して表現できない手作業の味わいを残すことでジャカード織本来の魅力を表現しています。
2.小林当織物株式会社
戦後間もなく服地生産を開始した桐生で有力な機屋の一つです。
資料室には創業当時からの5万点以上のスワッチを保管しています。この資料を元にアレンジを加え、メーカーのあらゆる依頼に対応し、新たな素材を生み出しています。
和装の雰囲気を取り入れた生地、天然素材中心のコレクション、上質な素材を使って多彩なテキスタイルを絶え間なく産出。ミラノ・ウニカなど海外での出展にも積極的で、国内外でその存在感を示しています。
3.ミワ株式会社
ティッシュラメハンド・スクリーンによる、グリッター・プリント加工、フロック・プリント加工ができる自社工場保有しています。伝統的なジャカード織り技術にプリント技術を組み合わせたハリのある生地から、多重織りの立体的な表情を持ちつつ、ソフトで落ち感のある素材まで幅広く展開しております。
効果的なラメ使い、光沢のある素材を用いて他社と差別化できる素材の生産を得意としています。
ぜひお手にとってご覧ください。
以上 山縣さんからの お話でした。
いま 在るものを大切にして
愛着が沸く新しいものを作っていく
洋服が素敵なことは勿論ですが
心の美しいwrittenafterwards
ご興味頂けましたら嬉しいです。
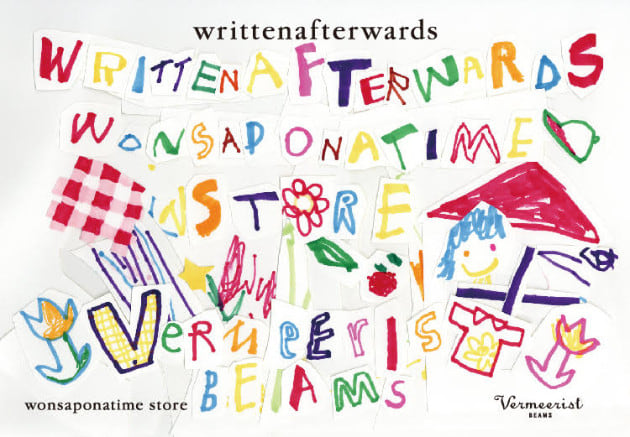
「wonsaponatime store」
2020年6月18日(木)販売スタート
※無くなり次第終了
Vermeerist BEAMS
☎︎03-5771-5745
イベントの詳細は こちらから御確認下さいませ
https://www.beams.co.jp/blog/vermeerist/59151/
どうぞ宜しくお願い致します。
大場