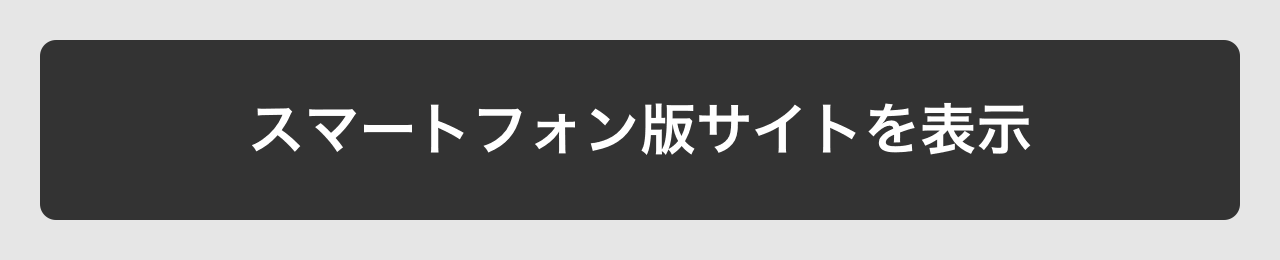本日はHYDRODYNAMICA / 5'8 GOLDEN MEAN MACHINEをご紹介させていただきます。
今回も前回同様に上記リンクの説明は省き、「一体どんなボードなのか?」というところに焦点を当て、個人的な主観満載でお届けいたします。

ノーズとテールを垂直にパツっと切ったようなシルエットが特徴のトライフィン。

ノーズのロッカーはまぁまぁある方なので、多少掘れている波でもテイクオフはし易いはずです。

「流体力学」をサーフボードのシェイプにも活用しているHYDRODYNAMICAのディケールがこちら。
サーフボードのシェイプに学問的な要素を取り入れているって今まで聞いたことありませんでしたが、このボードを完成させるにあたり、シェイパーのDaniel Thomson(ダニエル・トムソン)が8年という歳月をかけて制作したのがこちらのGOLDEN MEAN MACHINEになります。様々な要素を取り入れつつ、デザインを0からスタートして完成までにここまで時間をかけたボードというのも、私が知る限り、HYDRODYNAMICAがはじめてなのではないでしょうか。HYDRODYNAMICAを率いるRichard Kenvin(リチャード・ケンビン)をはじめ、シェイパーのDaniel Thomson(ダニエル・トムソン)も然り、サーフボードに対する確かな拘りが半端じゃなく強いことが伺えます。このことを踏まえても、日本ではまだ知名度が深く浸透していないプロジェクトだとしても、本国アメリカで抜群の人気を誇っているのも私には理解できます。Pilgrim Surf+Supplyオーナーのクリスも、このGOLDEN MEAN MACHINEの愛用者の1人でもあり、本国のPilgrim Surf+Supplyでは入荷する度に即完売してしまう大人気ボードなのです。クリスのオフィスにもこのGOLDEN MEAN MACHINEが置いてあったので、前回のニューヨークサーフトリップの時に借りて乗っておけば良かったなぁなんて今では少し後悔しています。

日本では製造が禁止されている(輸入はOK)XTRのエポキシ素材を使用している為、軽くて丈夫なのが大きな特徴と言えます。
HYDRODYNAMICA主催のRichard Kenvin(リチャード・ケンビン)は言います。「XTRこそ今まで試した素材でベストだ」と言うほど、そのクオリティの高さは折り紙付き。ノーズからテールまで比較的ストレートなアウトラインで、レイルは少し丸みを残したままにしているのも注目すべきポイントです。逆にレイルを薄くし過ぎてしまうとホールド感はズバ抜けて良くなりますが、波のフェイスに食い込み過ぎてしまい、操作性能が落ちてしまいます。この辺りはスラスターに匹敵するトップターンを可能にするならば、このほんのり丸みを残したレイルは、その操作性能を助けてくれる大きな役割を担っていると言って間違いないと思います。

そして特徴的なノーズの形。まるでシャベル(スコップ)のような形から、「ショベルノーズ」という言い方もします。ではこのデザインがどのような効果を発揮してくれるのか考えてみます。まず想像していただきたいのが、もしこのように先端部分をカットしていなければ、5'8"の長さが6'2"くらいの長さまで伸びると仮定してみます。それでも実際にテイクオフをする時は、ノーズ(先端)が水面に接することはまずありません。それは前述した「ロッカー」の有無にも大きく関わってきますが、先端が水面に触れてしまうとノーズから板が沈んでテイクオフ(波の上に立つこと)が出来なくなってしまうからです。なのでこのデザインの大きな意味は?と聞かれれば、不要な先端部分をカットすることによる「軽量化」を最大限求めたデザインであることを理解しておかなければなりません。では軽い方が良いのか?ならば全てのボードの先端をカットすればいいのでは?と思う方もいらっしゃるかと思いますが、それは一概には言えません。このGOLDEN MEAN MACHINEで言えば、軽量のXTR素材を使用していることも、このショベルノーズに設定した一つの大きな要因であると私は考えています。

続いてスクエア型に近い幅広に取られたテール部分。これにも実は深い意味があります。使用している軽量のXTR素材のデメリットを先にお伝えさせていただくと、その一つに「強風に弱い」ということが挙げられます。サーフボード本体が軽いと、強風の具合によって風力に負けてしまい、テイクオフがしづらくなってしまうこともあります。エポキシボードを持っている方ならば、特に強いオフショアが吹くとテイクオフがしづらいという経験をお持ちだと思います。そんな時に役立ってくれるのが、この広く取られたテールなのです。テール幅が広めに取られている分、水面に接する面積が広くなります。「水面に接する面積が広い=浮力が増す」すなわち、軽量化を第一に考えられたボードだとしても、テイクオフがしづらければ意味が無いので、このテール幅はそんな不安を払拭してくれる役割も担ってくれているのです。

SIZEは 5'8" x 19 1/2" x 2 1/2"。HYDRODYNAMICAがこのGOLDEN MEAN MACHINEを「ハイパフォーマンス Mini Simmons」と位置付けている通り、 一般的なスラスターに近いサイズ感でデザインされています。

そしてこのオンフィン(取り外しが出来ないフィン)にも大きな拘りが。実はこのフィン、我々日本人には特に馴染み深い「竹」で出来たフィンなのです。竹素材の大きな特徴としてまずお伝えしたいのが、「柔と剛2つの顔を持つ理想的な素材」だということ。竹本来の強靭さには不釣り合いな柔軟性をも兼ね備えており、その素材にいち早く目を付けたのが、チームHYDRODAYNAMICAなのです。加えて通常の木材よりも遥かに軽く、まさにこのGOLDEN MEAN MACHINEには打ってつけのフィン素材だと言えるでしょう。実際このボードを持ってみると、その軽さに驚いてしまう方がほとんどだと思います。加えてオンフィンならば、フィンボックスや金具等の余計な重量をかけなくても済む為、軽量化に特化するという点では、まさにこの上ない組み合わせなのです。

そして比較的浅めに設定されたチャンネル(ボードに溝を入れること)がさらに水の流れを増進させ、程良くスピードのあるライディングを楽しめるという構造。実際にチャンネルの入ったボードに乗るとよく分かるのですが、チャンネルが無いボードと比較すると、遥かにボードが前に進むことが感じ取れます。それはこの水面に接するチャンネルが水の流れる「川」のような役割を担ってくれていて、パドリングでもライディングでもダックダイブ(ドルフィンスルー)の時でさえ、その推進力は肌で感じることができます。そして画像ではなかなかお伝えしづらい部分ではありますが、GOLDEN MEAN MACHINEのコンケーブは、ノーズからテールまでにかけて、深いシングルコンケーブが入っているのも大きなポイントに。この深く入れられたシングルコンケーブによって水の流れを確保し、よりスピーディーなライディングを実現しています。GOLDEN MEAN MACHINEについて書いていて思ったことは、シェイパーであるDaniel Thomson(ダニエル・トムソン)然り、HYDRODYNAMICA主催のRichard Kenvin(リチャード・ケンビン)然り、使用している素材や細かなディティールまで一切の抜かりが無い、全て計算し尽くされた完成形であるということ。全てのディティールに深く確かな意味を持ち、サーフボードにおいてここまで計算し尽くされたボードが他にあるのでしょうか。はっきり言って物凄いボードだと思います。
Richard Kenvin(リチャード・ケンビン)率いる、1940年代~1950年代にカリフォルニアで名をはせたBob Simmonsのコレクションを現代の理論を使って復興させようとしたプロジェクトチーム。Hydrodynamicaのサーフボードを通じ、過去のサーフボードから現代のサーフボードへの進化を体感することができます。主なメンバーはSimmonsのシェイプを体現するJohn Elwell、Hydrodynamicaの総括をするRichard Kenvin、KeelフィンクラフトマンのLarry Gephart、シェイパーのHank Warner、Larry Mabile、Carl Ekstrom、そしてDaniel Thomsonで構成されています。Simmonsのプレイニングハル理論を使って、未来系のサーフボードを作り上げるプロジェクトとして、アメリカ西海岸を中心に幅広く活動しています。
HYDRODYNAMICA / 5'8 GOLDEN MEAN MACHINE
SIZE:5'8" x 19 1/2" x 2 1/2"
No.:36-75-0025-302
PRICE:¥192,000- +TAX ¥134,400- +TAX(30%OFF)
続きはまた次回