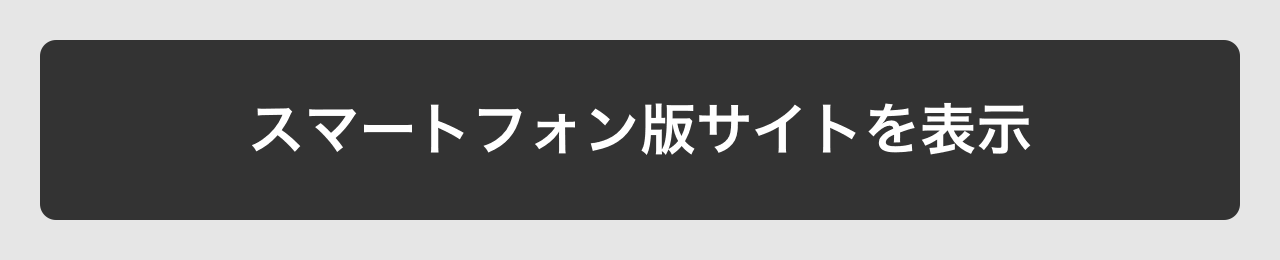今回は知る人ぞ知るオーストラリアが誇る最高のサーフムービー、「MORNING OF THE EARTH」のお話をさせていただこうと思います。

その前に、何故今になって1971年公開の「MORNING OF THE EARTH」?と感じる方もいらっしゃるかもしれません。その理由は、Pilgrim Surf+Supplyもかなりお世話になっているRIDE SURF+SPORT(以下RIDEさん)にて、この「MORNING OF THE EARTH」リマスター版の上映会が行われるということで、ご招待いただき行ってきたのが理由です。実は招待と同時に、Christian Beamishの日本代理店、JOY SURF JAPANのNathan(ネイサン)からも、「お前(私)はこの日ここ(RIDEさん)に来て、この映画をちゃんと観るべきだ」とわざわざメールをもらっていたので、行かないと怒られる(笑)というのは冗談ですが、行くべきだと判断して行ってきました。はじめにお伝えしておきますが、恥ずかしながらわたくし「MORNING OF THE EARTH」はまだ観た事が無かったので、個人的にもこのタイミングでちゃんと観られることを嬉しく思っておりました。

上映会と同時に、Pilgrim Surf+Supplyでも以前大盛況の末に幕を閉じた「THE SURFER'S JOURNAL」のイベントもRIDEさんで同時開催していたので、日本版編集長の井澤さんにもPilgrim Surf+Supplyでのイベント開催のお礼と、改めてご挨拶が出来て良かったです。Pilgrim Surf+Supplyでもやっていただいた、このWINDOWを広々と使ったレイアウト、やっぱりいいですね。

RIDEさんならではの「THE SURFER'S JOURNAL」とのスペシャルT-shirtsやParkaなども陳列されていました。Pilgrim Surf+Supplyの入口にも飾ってある「Litmus(リトマス)」のアート作品もRIDEさんにはあります。リトマスもサーファーなら避けては通れない、必ず観て欲しい映画の1つです。

そして間もなくして上映会の前に、THE SURFER'S JOURNAL日本版編集長の井澤さん(左)と、RIDE柴田さん(右)のお二方によるトークショーがスタート。THE SURFER'S JOURNAL日本版創刊の経緯や、井澤さんがサーフィンを始めた1972年(「MORNING OF THE EARTH」の日本での公開は1972年)当時の日本でのサーフィンのあれこれや、私たちが知らない日本サーフの歴史について等々、非常に興味深いお話をお聞かせいただき感謝でした。1972年当時にやっと「リーシュコード(サーフボードと後ろ足を繋ぐコード)」が普及されてきて、井澤さんもフィンに自分でドリルで穴を開けてリーシュを結んでサーフィンをしていたそう。※1972年当時は「リーシュカップ」はもちろん無い時代&リーシュコードも2021年現在にあるリーシュとは到底言えない、ただのゴムを通して結んでいたそうです。その為、ワイプアウトした時に離れたサーフボードが、ゴムの伸縮によって自分の方向に向かってきてしまうという、想像するとなかなか恐ろしいリスクと戦いながらサーフィンをしていたのです。ゴムを足首に直巻きするのも想像するに、かなり痛そうです、、、もちろんそれ以前は全てノーリーシュが基本だったんですから、泳いでボードを取りに行くのは当たり前の時代だったんですよね。昔の方はここで相当な泳力を磨かれたんだなと勝手に予想してしまいました。

Pilgrim Surf+Supplyではお馴染みのこちらのFin Window。お店にいらっしゃったことのある方なら、お分かりの方も多いと思いますが、ヴィンテージフィンコレクションが展示してあります(非売品)。1960年代後半から1980年代頃の、実際に使われていたフィンが所狭しとレイアウトされています。中にはプラスチック製のフィンや、ゴム素材で覆われたフィンなど今では考えられない、本当に機能するの?と疑ってしまうようなフィンが並んでいますので、気になる方はこの辺もぜひチェックしてみてください。先人のサーファー達が、どんな風に、どんなライディングを狙ってフィンの制作にあたっていたのか、想像しながらこのヴィンテージフィンコレクションを見るのが個人的には楽しかったりします。昨今ではEllis Ericsonが開発したパワーブレイドフィン然り、フィンを変えるだけでサーフボード自体の動きが大きく変わるのですから、やっぱりシングルフィンは究極であり、一体これから先、どれだけの経験と知識を得られるのか、終わりなき旅はこれから先もずっと続いていきそうな気がしています。だからこそやっぱりサーフィンは面白いですし、下手だからまだまだうまくなりたいですし、きっとこれから先も同じようなことを私は言ってると思いますね。

そしてフィンの下の方に開いたこの穴こそが、先程井澤さんが仰られていたリーシュを付ける為にドリルで開けた穴です。今はサーフボードには必ずリーシュカップが付いていて、リーシュコードもどんどん良くなっているので、時代は本当に進化しましたよね。サーフィン以外でも現在私たちが日常で当たり前のように使用しているものも、当然昔は無かった訳であって、そこには先人の知恵と発明と、並々ならぬ努力があってこそ産み出されたものであって、、、と考えるとPCも携帯電話もネットも何も無い時代に何かを発明して、それを世の中のスタンダードにしてしまった人がいるって、やっぱりスゴイことだよなぁーと改めて考えたりもします。

色々話が脱線してしまいましたが、そろそろ本題の「MORNING OF THE EARTH」に話を戻します。1971年公開の映画ですから、撮影が行われたのは恐らく1969年・1970年でしょう。この時はまだリーシュコードが無い時代なので、もちろん全員ノーリーシュです。簡単に歴史をおさらいすると、この当時はちょうどショートボード革命が起こって少し経った時期であり、サーフボードは5ft台の短いものから7ft台のミッドレングス、セミガン・ミニガンなどが新たに登場した時代でもあります(この辺りの歴史を紐解きたい方は、2009年公開の映画「GOING VERTICAL」が特にオススメです)。「MORNING OF THE EARTH」の内容に関しては、まだ観てない方もいらっしゃると思いますので、詳細まではここに書き記しませんが、個人的な感想のみに留めておきたいと思います。というよりも、とてもじゃありませんが、この映画の解説や時代の背景などなど、全てこちらのBLOGでご紹介するのは正直言って今の私には無理です。それほどこの映画は、私のちっぽけな知識や経験で簡単にまとめられる映画では無いということも、念を押して追記しておきます。そして「お前(私)はこの日ここ(RIDEさん)に来て、この映画をちゃんと観るべきだ」とメールをくれたネイサンにも、この場をお借りしてお礼を言いたいと思います。来てよかったーって本当に思いました。この映画を観てまず思ったことは現在から50年、半世紀も前の時代に、オーストラリアやアメリカではもう既にこんなことまでやってのけていたのか!というのが率直な感想です。今では世界でも名高いサーフポイント(毎年世界大会が行われるほど)として有名なバリのウルワツが世界中に広く知れ渡ったのも、実はこの「MORNING OF THE EARTH」の映画がきっかけだったり。とにもかくにもこの映画が昨今のサーフシーンに及ぼした影響は数知れず、偉大過ぎる先人のサーファー(もちろん錚々たる面々が登場しています)にただただ脱帽しました。

そしてPilgrim Surf+Supplyのレコードコーナーには、この映画「MORNING OF THE EARTH」のサウンドトラックレコードがオープン当初からあります。この映画はサーフィンのみにあらず、音楽としてもかなり高い評価を受けています。それをPilgrim Surf+Supplyのオープンに合わせて「MORNING OF THE EARTH」のサウンドトラックを真っ先に導入したオーナーのクリス。サーフィンはもちろん、音楽やアート等々、あらゆる分野に深く傾倒しているクリスの頭の中には、一体どれだけの歴史や知識が凝縮されているのか。どんな生き方をしてきたら、これだけのありとあらゆる知識を習得できるのか。本当に謎です。音楽にしても1970年代の楽曲をカバーしている現代アーティストもたくさんいて、現在私たちが使っているようなサーフボードのデザインも、ほぼ1970年代には既に発表されているものがほとんどです。そう考えると1970年代が現在にもたらした功績や歴史や文化は、個人的にも無視できないとても重要な時代なんじゃないかと思ったりもします。あり得ない話ですけど、もし時をまたいで旅行ができるならば、確実に1970年代を私は選びます。あり得ない話ですけど。

見開きに登場しているこの「MORNING OF THE EARTH」のジャケットにも使用されているサーファーは、オーストラリアのレジェンド、Michael Peterson(マイケル・ピーターソン)。世界中から彼の名の頭文字を取った「MP(エムピー)」という愛称で広く親しまれています。そしてMPと聞いて「あれ?どっかで聞いたことがあるような?」もしくは既にご存知の方も多いと思います。それもそのはず、MPが発明したEGG(タマゴ型のサーフボード)は今現在もなお「MP EGG」として、世界中の様々なシェイパーがこぞって真似(MPへのリスペクトやオマージュへの意味合いが強くあると思います)をしていたりするのです。私も知人からANDREINIのMP EGG7'4"を借りて乗ったことがあるのですが、これが7'4"のレングスとは思えないほどに軽快なターンを実現し、尚且つテール側に適度に立ったエッジが効いていることで、程良いホールド感も感じ取れました。それが私のはじめてのMP EGGに乗った時の感想です。終わってすぐに知人に「MPメッチャいいですねー!欲しいです!」って言ったことを今でも鮮明に覚えています。MP EGGの真骨頂はシングルからダブルに入れられたコンケーブによって生まれる、高い操作性能にあるのではないかと私は感じています。今のトライフィン(ショートボード&コンペティターボード)に見られるコンケーブは、シングルからダブルに入っているのが主流です。言うならば、現代ショートボードの基礎とも呼べるこのコンケーブは、Michael Peterson(マイケル・ピーターソン)によって生まれたものなのではということになります。そしてもちろんMPが開発したEGGはコンケーブのみにあらず、絶妙なアウトライン、特にややエッジの効いたテール側に個性がより強く反映されているように私は感じます。ぜひ機会があればお試しいただくことをオススメいたします。RIDEの柴田さんが面白いお話をされていたので、ここで少しご紹介させていただきます。柴田さんが上の画像にあるMPが乗っているボードのディメンション(サーフボードのサイズ)について、Andrew Kidman(アンドリュー・キッドマン)に聞いてみたそうで、その返答にはこうあったそうです。「5'8 x 20 x 3 1/4」(かなりうる覚えですが、これくらいのディメンションであったことは間違いないと思います)。レングスとワイズはまぁまぁ普通のショートボードのサイズですが、厚みがロングボード並みに分厚いことが分かります。そしてこの元祖とも言うべきMP EGGボードのフィンにご注目ください。見る限り、9.5くらいありそうな長いフィンが付けられています(現代では7か7.5くらいのフィンセッティングが一般的でしょうか)。そんな今ではなかなか考えづらいフィンセッティングで、こんなにキレイなラウンドハウスカットバックをキメているなんて、私には到底無理な話であり、シェイパーとしてもサーファーとしても超一流なマイケル・ピーターソンはやはり只者ではありません。当時世界最高峰のサーファーとの呼び声が高かったのは、間違いないと思います。
色々話が脱線して長くなってしまいましたが、個人的には「MORNING OF THE EARTH」の映画を観れたことによって、サーフィンはもちろん人々の暮らしや本当に必要なものはなんなのか、自分自身に置き換えて考えさせられたとても良い機会になったと思います。
もし機会があればぜひ「MORNING OF THE EARTH」を観てみてください。
それではまた