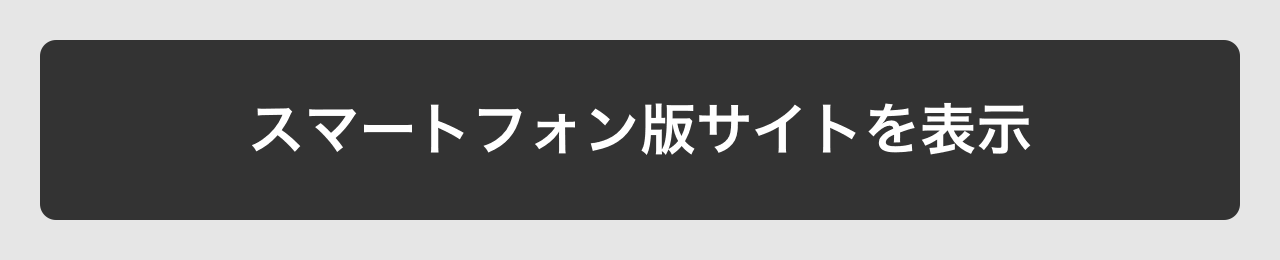OPNやローレル・ヘイローとのコラボでも知られるNYの鬼才ドラマー、イーライ・ケスラーの最新アルバム『icons』がオススメです!

【限定クリア・ヴァイナル仕様LP】Eli Keszler / Icons <LuckyMe>
価格:¥3,960(税込)
商品番号:29-24-0495-813
シンセと環境音と彼の繊細なドラムを組み合わせて作られており、ミニマルテクノからアンビエント、ブレイクビーツ、フリージャズが渾然一体となった秀逸な1枚です。今回はアメリカの抽象主義や同国の1920年代ジャズエイジが舞台のフィルム・ノワール、帝国の衰退といった事柄から着想を得たそうで、本人が世界各地で録りためていたという環境音も聞こえてきます。彼の頭の中のイメージの断片がシャッフルされたような景色が浮かんでくる、それも明確なストーリーがなく漂っているというような感覚です。そこになんとか骨格を与えているのが彼のドラム。全体的に音数を抑え、さらに疾走感のあるパートでも音量はあえて小さくしている点が巧みです。音色も独特で、テクノのような無機質さと人力ならではの有機的な質感が両立しています。それら全体の要素が効果的に働くことで、彼の思い描いている繊細で微妙な世界が浮かび上がってきます。
さて、そんな彼の音楽を聴いていると、以前に書いた“わかりやすさ”と“わかりにくさ”のようなことを考えてしまいます。今回もやはり結論は同じなのですが、また違った視点から綴っていきます。ずばり、虚と実という言葉から。
この2つの言葉はそれぞれ反対の意味がくっついたもので、虚というのは仏教では虚空と呼ばれ、古代インド哲学ではアーカーシャと呼ばれる長い歴史を持つ言葉です。意味としては、思い切って簡略して言ってしまえば空っぽということ。実というのはその反対で中身のあることや、中身そのものを意味します。たとえば油断して隙をつかれることを「虚を衝かれる」と言います。この使い方のルーツは武術と思われますが一般的にもよく言われますね。東洋医学では病気に対する抵抗力が少ない状態を虚、病気に対する抵抗力がある状態を実として考えます。
非常に興味深いのは、江戸時代の浄瑠璃及び歌舞伎の作者、近松門左衛門による『虚実皮膜論』という論考です。芸の真実は、芸術的虚構(=嘘)と事実との間の微妙なところにある。虚構があることによって芸の真実味が増すということを述べています。
ここでご紹介したい本があります。内山節『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』です。狐に騙される、化かされる、つままれるという言い方を一昔前の日本人はよく使っていたのに、いつ頃からか使わなくなってしまった。それはいつからだったのか、そしてそのことは何を意味しているのかを追った内容です。端的に言うと、1965年頃、高度経済成長期からそれまでの日本人の生活が一変し、科学を重視する世の中になった、人間と自然との関わり方が変わってしまったことなどが挙げられています。
キツネに化かされたということ以外にも、主に秩父地方で伝わるオオサキという架空の動物の話が印象的で、どのようなことをする動物であるのかは割愛しますが、この本を読むと、これらの存在が村の中の人間関係に起こるギスギスしたものを解きほぐしてくれていたことがわかります。つまり科学的思考では嘘となる話が日常に溶け込んでいることで、実は社会の秩序が生まれていたということです。世界各地で伝わる神話にも教義として機能しているものは多くあり、例えば西洋建築物で見られるガーゴイルのように、雨樋の機能だけでなくこの姿が建築物と同居していることで、実は教育の役割を果たしているという話を哲学者の國分功一郎も語っていました。親子で散歩しているときに子供が親に、あれは何かと尋ねる様子を思い浮かべるとわかりやすいですね。
また、我々が何気なく考える歴史というものも、改めて見つめ直す視点を持つことの大切さも述べています。一般的に歴史というのは、原因→結果から組み立てていくので、過去から未来に向かうに従って発展、進化しているという前提で考えられてしまっているということです。これを進歩史観と言います。たとえば、我々は20年前には存在しなかったスマートフォンを軽々と使いこなしていることは科学技術の視点で言えば進化ですが、使っている全ての人が原理を分かっていて使っているわけではないので、果たして人類としての進化になるかといえばどうなのかということですね。この進歩史観でつい物事を考えてしまい、我々は歴史から学ぶことを軽視する方向に向かっているところはないか。思い当たることはあちこちで起きている気がします。
(②に続きます。)