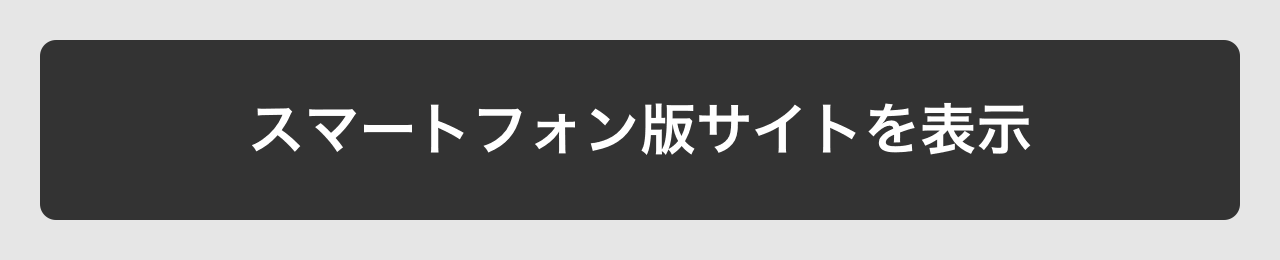また厳しい暑さが戻りましたが、湿気は少し和らぎ夜は涼しかったりと、次の季節の到来を予感させます。しかし、当店では熱い作品の入荷が続いています! そのひとつは、奇才マシュー・ハーバートの名作『Bodily Functions』の復刻盤です。ハーバートといえば、食べる音や寝る音、洗う音など身体から出る音のみで構築した前作アルバムも記憶に新しく、ライブ時にはグローバリズムへの反発としてそれを象徴するアイテムを破壊する音をサンプリングしてビートを組むなど、エキセントリックでポリティカルなパフォーマンスも有名ですね。
本作はハウス、テクノなどのダンスミュージックとジャズが軸になった官能的で美しいサウンドが特徴で、彼の作品の中でも最も美しいアルバムとして知られています。しかし、ミュージックコンクレートなどの手法を駆使して彼らしいメッセージも詰め込んでおり、気持ち良いグルーヴに加えて時折りゾクッともさせられるバランスがなんとも言えません。

【3LP】Herbert / Bodily Functions (2021 Re-Issue) <Accidental>
価格:¥5,060(税込)
商品番号:29-74-0289-526
(②はこちらからどうぞ)
さて、前回までで書いた進歩史観についてですが、これを助長させるものとしてテクノロジーの進歩があることは容易に想像がつきます。そして、本題である虚と実の話にも繋がっていく部分があると思っています。
我々は部品コストの低下や製造方法の効率化などのおかげで、たとえばテレビなどの電化製品が、2年前のものと同サイズ同スペックでも当時より安く買えるというようなことを体験し続けてきました。これはムーアの法則と呼ばれ、およそ50年に渡って続いてきましたが、集積回路をベースにしたものは、2025年までには限界を迎えると指摘されています。しかし、一つの発明が他の発明と結びつくことでイノベーションが加速するという収穫加速の法則というものもあり、こちらは今後も続く可能性が高いと言われています。
この恩恵に授かる我々人間側は、一度味わった喜びや快適さをいつの間にか当たり前に思ってしまいますが、実はそれだけでなくもう少し違う感覚というのも味わっているようです。今、AIに頼っている部分が生活の中で日に日に増えているなかで、AIがある課題を達成すると我々はすでにそれを知能とみなさなくなり、AIでないと認識してしまうところがあるそうです。これは「AI効果」と呼ばれています。
果たしてテクノロジーの進歩はどこに向かっていくのでしょうか。いつか映画『マトリックス』や『ターミネーター』のような世界が来てしまうのでしょうか? 2009年にスイス連邦工科大学の知能システムに所属する研究者たちがある実験を行いました。定められた枠内で、複数の小型の車輪付きロボットに「食べ物」を見つけるように指示をし、見つけたら備え付けのライトを点滅させ、他のロボットにも一緒に回収に向かわせるように設計。見事回収できたロボットには得点を与え、フェイクとして一緒に並べた「毒物」を回収してしまった場合は得点を失うというルールだったそうです。そして、実験を終えるたびに、最も成功したロボットの人工ニューラルネットワークを他のロボットにも複製し進化させました。これを15代に渡って繰り返すと、一部のロボットはプログラム内容を無視して、「食べ物」を見つけてもライトを点滅することを止めました。さらに、「毒物」を見つけたらわざとライトを点滅し、他のロボットを「毒物」に誘導するロボットも現れます。ロボットの改良が数百代まで続くと、ついにはすべてのロボットが点滅を止めたそうです。
この実験から考察出来ることは色々とあるわけですが、我々の生活でAIに支えてもらう部分が増え続け、そのこともAIの成長にも気づかないうちに、いつの間にか彼らが我々の知能を超え、自身のために嘘をつくことを覚えたとき、それを管理するはずの人類にとってどんな未来が待ち受けているのでしょうか? 収穫加速の法則を考慮するとその「いつか」というのも想像以上に早いのでしょうか。

ダークな雰囲気と、電子音と人力ドラムの錯綜がかっこ良い、モーリッツ・ヴォン・オズワルド・トリオの最新作は、こんなディストピアなもしも話のサントラとしてもハマってしまいそうです。惜しくもトニー・アレンが他界してしまったこともあり、新たなドラマーにベテラン、ハインリッヒ・クーベリングを、そして現行テクノシーンの代表格ローレル・ヘイローも迎えた渾身の一枚です。
Moritz Von Osward / Dissent <Modern Recordings>
価格:¥2,750(税込)
商品番号:29-08-0371-494
【LP】Moritz Von Osward / Dissent <Modern Recordings>
価格:¥4,180(税込)
商品番号:29-08-0372-494
この話や、以前の①で書いた虚実皮膜論やキツネに化かされた話などを踏まえると、嘘というのは良い意味でも悪い意味でも人らしさが詰まっている大きな要素なのではないでしょうか(動物の擬態にも似たところはありますが)。また、虚が「空っぽ」や「外形」を表すというところからか、「虚無」という言葉はあらゆるものに価値や意味を求められない、放心状態のようなネガティブな気持ちを表す意味を同時に含んでいるところも良いなと思ってしまいます。そういうところにこそ、人の深い部分があると思うからです。哲学者のニーチェはまさにそこに希望を見出そうとしていますね。
(④に続きます。ついにラストです!)