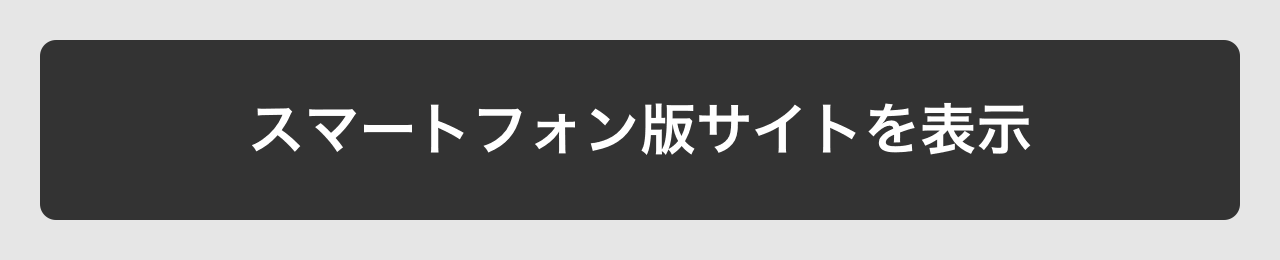正解は「人」です。
突然すみません。
こんな「なぞなぞ」があるほど、馴染み深いステッキ(杖)ですが、日本においては「ファッションアイテム」というよりも、「道具」として馴染んでいますよね。
突然すみません。今回は台風1号の発生記念に、雨天時には欠かせない傘のご紹介です。
それがこちら

普通の傘です。
が、注意書きに気になる箇所が

ステッキとして使用するなど…と。
ステッキと聞くと、なんだか紳士のイメージですね。
流石に、その使い方はしませんが、小学生くらいでしょうか。確かに「武器」として活躍させた時期が、僕にもありました。
この様に、色んな捉え方をできる「傘」ですが、どう捉えるのかが我々の住む日本とヨーロッパでは、大きく異なります。
「イギリスの人は傘をささない」と耳にしたことはありませんか?
日本のように、台風や豪雨が頻繁にというわけではなく、しとしと雨や、霧が多いとされるのがイギリス。雨に対する考え方も大きく異なります。
雨を凌ぐ方法とすれば、
・日本→傘、レインコート
・イギリス→ハット、コート
こんな感じでしょう。
日本的な解釈でいけば、雨に対しては、専用の「道具」が必要です。
反対にイギリス的に見るとどうでしょう。雨の日でなくても、ハットコートを着用するシーンは数多くあります。あくまでも「ファッション」の一部としての解釈で雨を凌いでいます。
そもそも、ヨーロッパに傘の文化が入ってきたのは18世紀と言われており、今で言うビーチパラソルサイズの傘をさしていたそうです。
今のイメージとは異なり、決してエレガントとは言えませんね…。
しかし、雨を「道具」で凌ぐ文化がなかったのですから、便利なことに変わりありません。
だんだんと小型化が進んでいき、英国紳士の手元は、サーベル→ステッキ→傘という様に変化していったのです。いざとなれば、「武器」として、またタキシード文化が根付くイギリスにおいて、タキシードでは良し悪しが付き辛い代わりに、周りと差をつける役目を果たした「ステッキ」。その両方の役目に、雨を凌ぐ「道具」としての役割を兼ね備えた傘ですから、それは直ぐにでも浸透するはずです。
そんな手元の変化は、ステッキの様に傘を細く巻く事で、お金を稼ぐ方々が誕生するほどまで根付いていたそうです。
こんなお話がある様に、傘を細く保つことは、紳士のステータスとなった訳です。
さて、そんな情報も踏まえてBEAMSの傘を見るとどうでしょう?
ハンドル

玉留め
スライド式なので、地下街などサッと通る時には、ここで留めるだけで大きく開く心配がありません。
手も濡れなくていいですね。


留め具

石突き

どうでしょう?
どこをみても、シュッとエレガントですね。
ちなみに広げると、こんな感じです。

結構すっぽり入ります。
相合傘もできちゃいます。
ちなみ相合傘も日本的な解釈の恋愛テクニック。イギリスでは、前が見えなくなるほど深く構え、チラチラと気になる方を見るそうです。そこで目が合えば…。
恋愛においては「道具」として使うんですね。
こんな紹介でしたが、いかがだったでしょうか?
梅雨入り目前のタイミング。是非気になった方は、店頭でお待ちしております!
ではでは。