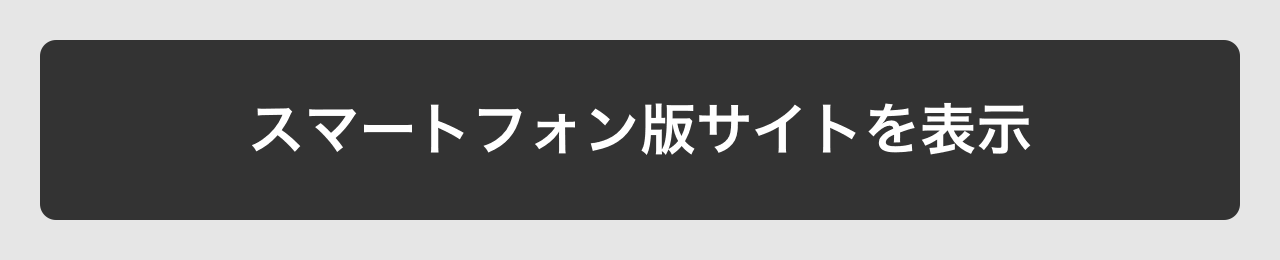ヒップホップやR&B、ソウル、ファンク、ブルース、ジャズなど、アフリカ系アメリカ人の方々が生み出してきた音楽の影響力は周知の通り計り知れませんね。そんなブラックミュージックの魅力はこのブログ上では書き尽くせないほどありますが、ほんの一部分でも改めて共有することで、皆様と深められるものがあれば良いなと思っています。
今回は”リズム”という観点から。裏拍の多用や、拍を伸ばして、アクセントの位置を変えていくシンコペーション。ビートを後ろに引っ張ることで独特のゆるさを生むレイドバック。これと似たもので、Questloveが叩いたD’angeloの『Voodoo』やJ Dillaで有名な、”ズレ”をあえて作ることで独特の快感を生むドランクビート。

こちらは、Slum Village による不朽の名作『Fantastic, Vol. 2』のリリースから20年を記念し、現行メンバーであるT3とYoung RJが、ヒップホップのインスト・カバー作で知られるUKのビッグ・バンド、Abstract Orchestraとタッグを組んだスペシャル・プロジェクト!
などなど、彼らが独自に発展させ、生まれたリズムというのは多く存在します。また、リズムが時間の経過の中で成立することを思うと、その時間の概念自体を変容させてしまう点も我々を驚かせてきたと思います。最近ではChris Daveなどが多用する、異なるBPMから同じ音の長さ(時間)になるものを抽出して、耳の錯覚を起こさせるポリリズムの一種、メトリックモデュレーションがその一つと私は捉えています。

Robert Glasperの新作アルバム『Fuck Yo Feelings』は、Chris Dave、Derrick Hodgeを中心に多くのミュージシャンとのセッションを収録しています。
昔の代表例で言うと、James Brown(以降"JB"と表記)にもあります。例えば名曲「Please Please Please」について。メインのコール・アンド・レスポンスが終わると一瞬全体の演奏が止まり、その後JBの声だけ再び歌い出し、再び全体の演奏に戻ります。今となってはあまり驚きませんが、当時はそのタイム感の正確さ、そもそも音が突然全部止まってまた何事もなかったように始まるということ自体に世間が驚いたそうです。また、彼のライブ映像は音楽好きなら一度は観たことがあると思います。彼を筆頭に、バンドメンバーも多くを緻密に繰り返します。それはギターの1フレーズから、曲の展開だけでなく、パフォーマンスも(終盤になると突然膝をつき、マントを掛けられながら退場しようとするも、途中でマントを振り払ってまたマイクスタンドのところに戻る、その動作を何度も繰り返すのは有名ですね)。それを見(聴き)続けていると時間の感覚がだんだんわからなくなってきて、なんともたとえようのない高揚感がやってくるのを感じます。
ここで、彼らのルーツであるアフリカ人による音楽の話になりますが、西アフリカの民族楽器ジャンべは聴いたことがあるでしょうか。複数の人々がジャンべを同時に叩くのですが(違う種類の打楽器のことも多々あります)、それぞれが違うリズムを叩いて、その中で共通項が生まれたり(融合したり)、離れたりを複雑に繰り返します。これによって、一種の錯覚を起こしているかのような気持ちよさを感じてきます。ポイントは一瞬でそう感じるわけではないところですね。あくまで時間の経過とともにそのように感じてきます。1人が5連符と3連符が交互に聴こえるように鳴らすことも多々あります。
このようなアフリカ人のリズム感覚については、遡ると19世紀後半には既にイギリス人の探検家がそのことについて綴っている資料が残っているほど、現代に至るまで多くの専門家が研究を続けてきたそうです。その中で、1980年代初頭に研究者のアラン・メリアム、そしてロバート・カウフマンが、アフリカの時間観念が違うからではという見解を示しており、これは先述の例をある種総括しているようです。※あくまで西洋音楽の立場から見ているものなので、厳密にはアジアのルーツ音楽なども、国独自のリズム感覚という意味で同じことが言えます(菊地成孔氏はこれを訛りと表現しています)。JBらがどれだけアフリカ音楽のルーツを知っていて、自覚的にこれをやっていたのかはわかりませんが、素晴らしいところは白人のポップスの中にその要素を組み合わせてきたことです。そしてこれは、冒頭に述べたシンコペーションや、ポリリズム、さらにはグルーヴ、スウィングの話とも繋がる興味深い話だと思います。
私も音楽をやっている身として、彼らのリズムを真似しようとするのですが、それが非常に難しいことを日々痛感します。では彼らがそれを生まれながらに身につけていたかといえば、確かに教会音楽であったゴスペルが現在R&Bやファンクに受け継がれているように、上述のJBやD’angelo、Chris Daveなど、多くのミュージシャン達が教会に通って下地を身につけていたということは周知の事実ですので、そうとも言えるのですが、とはいえ、やはり努力の賜物としか思えません。彼らのような複雑なズレを生み出すには正確なリズム感(≒タイム感)なしには不可能だからです。そして複数のリズムを同時に感じていくスキルも必要です。実際にChris Daveはテクノを再現した、無機質なほど正確で力加減もほとんど変わらないようなドラムを叩いたりもしており、それを交互に組み合わせたりしています。アフリカ系の人々がこれまでにアメリカで受けてきた辛い出来事を思うと、あくまで一個人の意見ですが、私としては彼らにとってリズムというのはアフリカ人としての財産であり、矜恃を示すようなものの一部とも思えてしまい、やはり尊敬の念を感じざるを得ません。