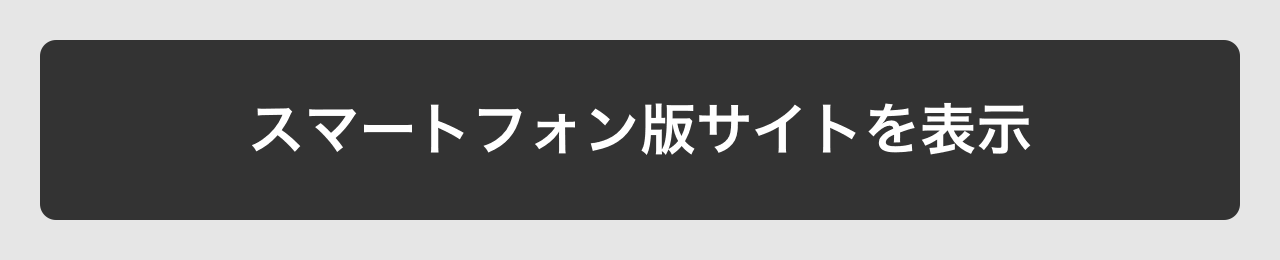皆様、こんにちは。
fennica STUDIOの水溜です。
“濱田窯 在る日の益子 濱田庄司登り窯復活プロジェクトの器たち”開催まで、あと一週間となりました。
本日もプロジェクトに参加した作家をご紹介します。

前回の登り窯復活プロジェクトにも参加していた<アンドリュー・ゲムリッチ>さん。
アメリカ・ミシガン州に生まれ、早稲田大学の留学を経て来日。
その頃に油絵を勉強しながら、焼き物の授業を受けたことがきっかけで陶芸を始めます。立体的なものを作ることが面白くなり、どんどん焼き物にのめり込んでいったそう。
「普段は一人で作っているので、たくさんの作家さんと一緒に共同作業が出来るのは新鮮です。笠間の作家さん達と交流することが出来たのは良かったです。」と、おっしゃっていました。



土そのものの味わいと質感が特徴の益子の土。灰釉とのコントラストが目を引きますね。
ぐい呑みや片口鉢、花瓶を中心にご用意します。

笠間生まれ、笠間育ち、イギリス人のお父様は陶芸家という<セレン のあ>さん。
実家の登り窯のエネルギーに魅了され、笠間に帰ったのを機に自分も陶芸家の道を志します。
お父様が強く影響を受けた『濱田庄司』、自分が惹かれる『登り窯』。
独立するタイミングで登り窯復活プロジェクトに参加し、この2つの要素が重なったことに興奮したといいます。


「伝統的なスタイルや、天然原料を用いた釉薬などクラシカルなアプローチで取り組んでいます。」
使って良いもの、素朴で丈夫、といった民藝の心を大切にしながら、モダンさも入れ込むようにしているという器は思わず見入ってしまいます。

大阪で生まれ育った<榎田 智>さん。
20代の頃は、ギターを持って沖縄を旅していたというバンドマン。
奥様のご実家が益子焼の窯元、という縁で益子に暮らし始めましたが、次第に土に触れてみたくなり、指導所やお義父様から陶芸を学びます。
「えのきだ窯先代の器に習って、その良さを元に益子焼らしい温かみのある器作りを心掛けています。」
普段使っている益子の土だと登り窯の火力で歪んでしまう可能性が高いと思い、土の配合を変えるなど実験的な制作をされたそう。


えのきだ窯の先々代が、益子で作っていたという代表的な急須。
登り窯ならではの重ね焼きの跡が残るリム皿などご用意します。

独立して2年、20代の作家<佐川義乱>さん。
幼い頃からもの作りが好きで、お母様の仕事(陶芸)の手伝いをするため、技術を学びに笠間の窯業指導所へ入ったのがきっかけ。
スリップウェアの技法を使い、笠間の土を泥漿(でいしょう)状にしたもので模様を描きます。
伝統的な中にも若さのある、新しい益子のデザインを感じさせると各方面で言われているそう。


いかがでしたでしょうか?
次回も引き続き、ご紹介しますのでお見逃しなく。

“濱田窯 在る日の益子 濱田庄司登り窯復活プロジェクトの器たち”
会期:4/27(金)~5/6(日)
場所:fennica STUDIO(BEAMS JAPAN 5階)
水溜