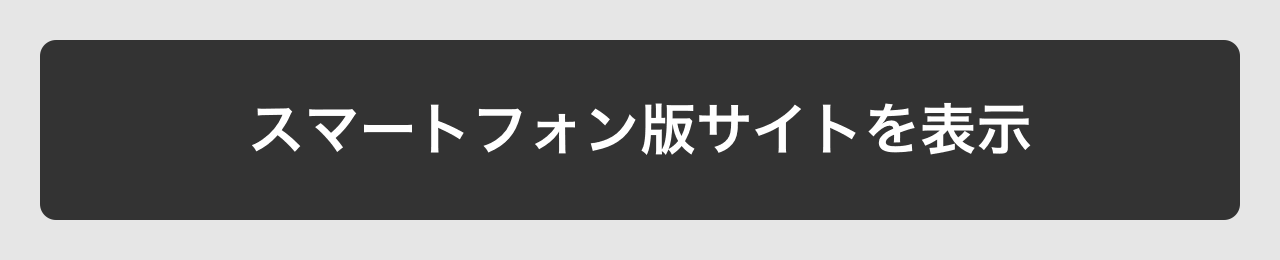(①はこちらからどうぞ)
その内容はというと、動植物の腐敗とそれを食糧とする土壌生物や発酵についてだけでなく、リサイクル、SF小説、積み木、バタ屋、経済など多角的な視点から分解または循環というものを深く考えてみるという作者自身の試みのようなものでした。そうしたエピソード一つ一つに感心したのはもちろんですが、個人的に特に面白いと思ったのは積み木についてでした。そもそも積み木というのは、フリードリヒ・フレーベルというドイツの教育学者が幼稚園という存在を生み出す際に、同時に考案したものだったそうです。この積み木を使って積み上げたり崩したり(崩れたり)を繰り返す事によって、多角的な視点を持つ力を養ったり、部分と全体という概念を獲得することが出来ることや、最後に遊具箱に積み木を戻すことで秩序を教えるなど、実は幼児期の子どもにとって有意義な経験をたくさんさせているということでした。
また、この「積む」という言葉にスポットを当て、「構成する」「組み立てる」を英語にした"composition"というのは音楽では「作曲」を意味し、動植物による死骸の「分解」を"decomposition"と書く、と述べていたところは、音楽好きとしてはやはり見逃せませんでした。先日、時事性の高いコンテンツで人気を集めている「Choose Life Project」という動画配信プロジェクトで、昨年7月に「ゴミと資本主義」というテーマでゲスト達が議論していたアーカイブを遅まきながら発見したのですが、そこで後藤正文さん(Gotch, Asian Kung-fu Generation)が同書について触れ、まさに上記の2つのワードを引用し見解を述べていました。それは、音楽もコードやメロディを分解・再構築して新しいものが生まれるという循環の中にいるというもので、さらにそれを受けて同じく出演者の篠田ミルさん(Yahyel)も、自身が楽器の演奏を出来ない代わりに、音源のパーツを買ってそれを組み合わせることで曲を作っていることや、ヒップホップのサンプリングのことを照らし合わせて、この発想が作曲の可能性を広げたという趣旨の見解を述べていました。
なるほどと思いながら聴いていたのですが、私はまた違う角度から色々と思い浮かべていました。"composition"と"decomposition"の間、つまり積み木でいえば、積み上げたものが崩れる瞬間の興奮についてです。それはドビュッシーやシェーンベルクが、明るい雰囲気なら長調、暗い雰囲気なら短調という西洋音楽史の中で使い分けられてきた2つの調性の法則を一緒くたにしてしまったことにも言えるでしょう。これが後々のジャズ史へと繋がっていきます。そのジャズのことでいえば、今の商業音楽の基礎ともいえるバークリーメソッドを駆使し、コードの分解をし続けるうちに、コードの機能性を失いノイズへと接近していったフリージャズの危うさにも。難解なプログレを壊したパンクの単純な3コードにも。エレキギターのフィードバックノイズの爆音がバンドのアンサンブルを掻き消した瞬間(シューゲイズ)にも言えるでしょう。

(右)アート・リンゼイとジョン・ルーリー率いるラウンジ・リザーズとの共演は、ノイズミュージック(正確にはノーウェイブ)とフリージャズが渾然一体となった一つの証拠ともいえそうです。そんなアート・リンゼイがプロデュースしたこちらもお聴き逃しなく!(左)バスキアが在籍していたことでも知られる「グレイ」もノーウェイブ・シーンを考える上では欠かせません。曲によってはブラックミュージック由来の洒脱さを見せてくるところがまた憎いです!
【LP】Tiago Nassif / Mente <Gearbox>
価格:¥3,300+税
商品番号:29-08-0327-494
【グレー・ヴァイナル仕様 / 限定盤LP】Gray / Shades Of...<Ubiquity>
価格:¥9,130+税
商品番号:29-73-0370-491

また、リディア・ランチを敬愛するニコラス・ジャーの作品からも、ノーウェイブが受け継がれていることを感じることができます。
Nicolas Jaar / Cenizas <Other People>
価格:¥2,750+税
商品番号:29-73-0368-491
【LP】Nicolas Jaar / Cenizas <Other People>
価格:¥4,620+税
商品番号:29-73-0369-491
著者も、積み木が崩れる時の息を呑む空気の緊張は新しい世界への兆しと説いているのですが、構築されていた前時代のスタイルが崩れる瞬間というのはそこにしかない大きな感動と意味があるものです。さらに同書では、割れた器を漆で修繕し再び使用できるようにする、「金繕い(金継ぎ)」の独特の美しさについてや、国語学者の大野普の仮説を引用し、昔の日本人の「時」という感覚は、凝固したものが解体された時に生まれるものだったということも紹介していました。これらを合わせると、肉体だけでなく我々の感性というのは、この世の中の原理と密着しているのだと気づかされます。このことをあえて言うこと自体、悲観的にいえば、我々が自然との接点を失ってしまっていることの裏返しかもしれませんが、今これからを生きるヒントは我々の感性がすでに知っていると言えなくもなさそうです。