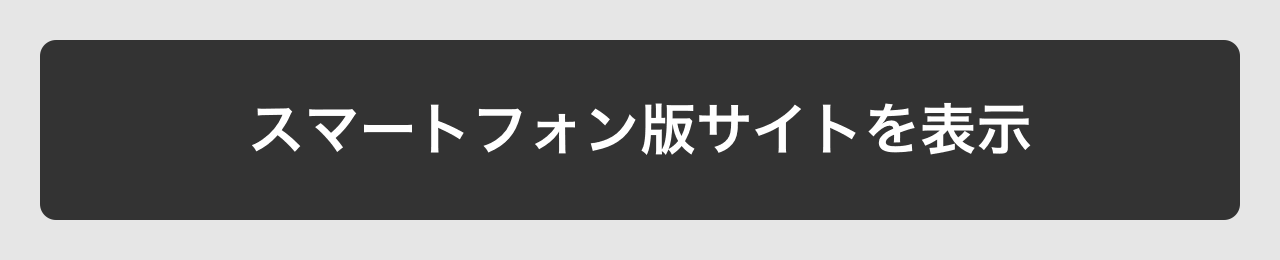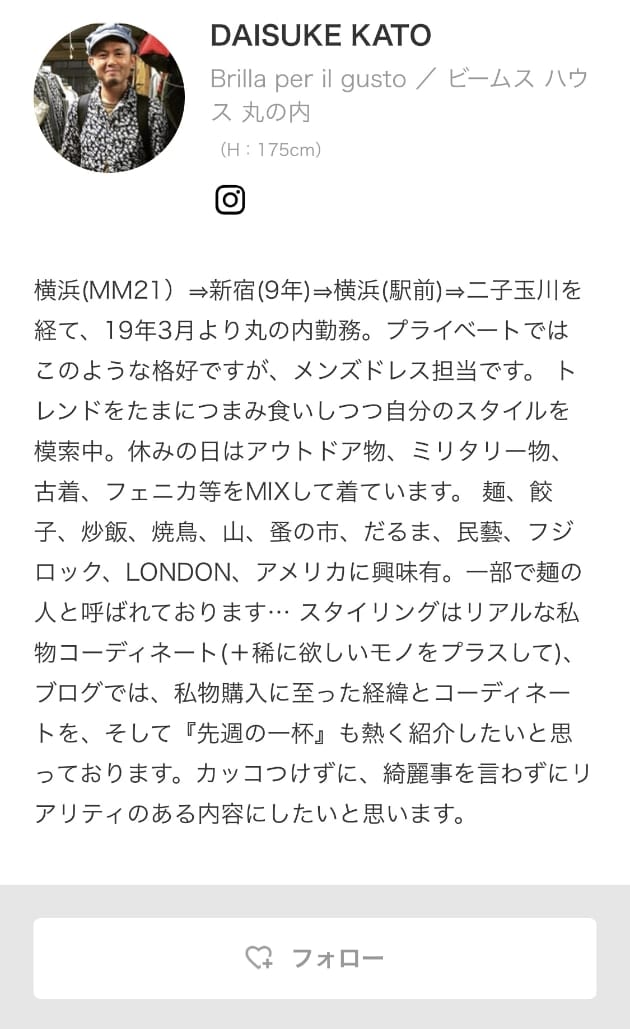こんばんは。
全国を巡回し、現在、東京の世田谷美術館で開催されている展示
を先日見てまいりました。
公式HPから概要を引用させていただきます。
日々の暮らしで使われていた手仕事の品の「美」に注目した思想家・柳宗悦(1889-1961)は、無名の職人たちによる民衆的工藝を「民藝」と呼びました。
本展は、美しい民藝の品々を「衣・食・住」のテーマに沿って展示するほか、今も続く民藝の産地を訪ね、その作り手と、受け継がれている手仕事を紹介します。さらには現代のライフスタイルにおける民藝まで視野を広げ、その拡がりと現在、これからを展望します。
私の補足的には、骨董品や古美術というイメージの敷居の高いものではなく、元々暮らしの中で使われていた道具に美を見出した民藝の名品と現在の作り手の紹介、そして現代の暮らしへの取り入れ方を提案する展示です。
東京駒場の日本民藝館や、静岡の芹沢銈介美術館が所蔵する日本の服や器、家具などの名品をメインに、欧米の暮らしの中で使われてた品々も展示されています。
会場の世田谷美術館は、砧公園という世田谷区の大きな公園の一画にあり、最寄り駅は田園都市線の用賀。駅からは徒歩20分程。バスも出ていますが、アップダウンがないのと、砧公園の雰囲気も良いので、散歩がてら歩きがオススメです。


個人的に感じた見所は、1941年の日本民藝館での「生活展」の再現を試みた展示。ショーケースや台に並べた博物館的な展示ではなく、民藝の品々で室内を装飾した見せ方は、当時としては画期的だったようです。


写真は展示の一部ですが、このエリアは写真撮影OKなのも嬉しい点です。
そして、2Fに上がると、ビームスのレーベル fennicaでの取扱いもある現代の作り手さん達の展示やインタビュー動画が流れるゾーンも興味深いです。
有名なところだと、九州の大分の小鹿田(おんた)焼が紹介されています。
私も3年程前に初めて小鹿田焼の里山を訪れましたが、現地の土を使い、一子相伝の家族経営の手作業で作られた陶器は、やはり温かみが感じられて魅力的です。




当時ブログ掲載許可をいただいた黒木さん、坂本さんの窯の写真を使用させていただきました。
そして最後の展示は、ビームスOB・OGであり、ビームス ロンドンオフィスのバイヤー兼fennicaディレクターを長年務め、現在は高円寺のショップ MOGI Folk Artのディレクター、テリー・エリスさんと北村恵子さんの私物コレクションの展示コーナーが有ります。

陳列だけでなく、世界各地のフォークアートと民藝品をどう現代の生活に取り入れるか?というスタイルを提案するインスタレーション形式ですので、より親しみや関心が湧くのではないでしょうか?

説明が前後してしまいましたが…私、今年の1月からMOGI Folk Artでスタッフとして週1回、基本的に月曜日に働いております。(ビームスも数年前から副業が申請をすればOKになりました。)
という訳で私は関係者ではありますが…そういうことは抜きにして、副業するなんて考えたこともなかった昨年から個人的にも楽しみにしていた展示でした。
実際に楽しんで学んで見ることができた2時間。インタビュー動画の展示もいくつかあるので、時間に余裕を持たれての訪問がオススメです。
MOGI Folk Artに関しては改めて紹介したいと思います。色々なメディアで紹介されていますが、BRUTUSさんの記事がわかりやすいかもしれません。
最後にある、MOGI Folk Artも含めた全国の有名民藝品店が集結した物販売場も圧巻の品揃えですよ。
今回の世田谷での展示は6/30(日)までと、残り2週間強となりました。民藝て何?という方から、民藝好きの方まで楽しめる展示だと思いますので、興味を持たれた方はぜひ訪問してみてはいかがでしょうか?
ブログ掲載に関しては、学芸員の方と広報の方から許可をいただいております。
3年前の展示も同じ学芸員の方が担当されたそうです。
アイノとアルヴァ 二人のアアルト展
というその時のブログもよろしければ、ご覧ください。
それでは、また明日お会いしましょう。
よろしければ、コチラからフォローやお気に入り登録もお願い致します。
ビームス ハウス 丸の内全体の投稿はコチラを。最後のフォローボタンを押していただくと私以外の当店全スタッフの最新投稿もご覧いただけますよ。
KATO