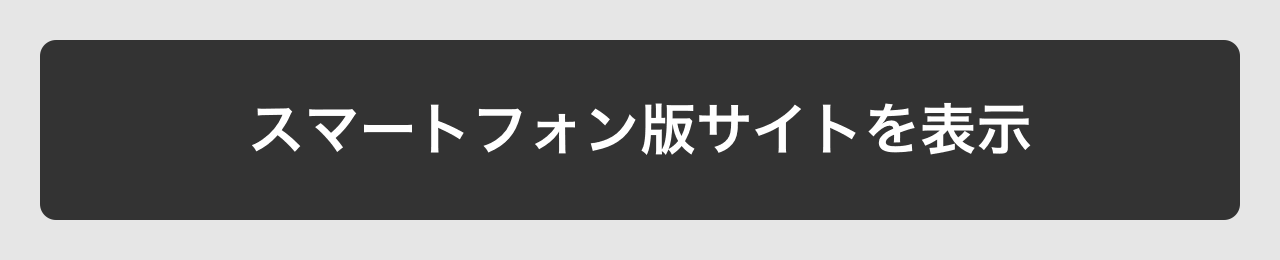こんにちは。BEAMS RECORDSスタッフの和田です。
気が付いたら夏が終わって一気に肌寒くなりましたね。秋のほどよく冷たい空気の匂いがふわっと感じられた時、自分は本当に幸せな気持ちになります。それだけで色々な曲のことやライブのことまで思い出して、なんだかいつもより音楽が自分に染み渡る感覚になります。
そんな気分の最近は、先日当店にも入荷したSam Wilkes, Craig Weinrib, and Dylan Dayのトリオ作品などをよく聴いてしまいます。入荷はしていませんが、このトリオに加えてChris FishmanとThom Gillの二人が参加したライブの音源をまとめたアルバム「iiyo iiyo iiyo」も素晴らしかったです!
Sam Wilkesは現在来日中でSam Gendelとの全国ツアーもやっていますので、気になる方は是非調べてみてください!自分も静岡で行われるフェスfrueで見に行く予定です♬
また、Sam Wilkesと並んでついついよく聴いてしまう作品がこちらです。
【LP】Jonah Yano / Jonah Yano & The Heavy Loopo〈Innovative Leisure〉
¥4,730 (税込)
【CD】Jonah Yano / Jonah Yano & The Heavy Loopo〈Innovative Leisure〉
¥2,860 (税込)
広島県出身でモントリオールを拠点に活動するシンガー・ソングライター Jonah Yano(ジョナ・ヤノ)が、彼のアンサンブル・バンドとともに収録した最新アルバム。
前作に引き続き、今作も素晴らしいですね..!ジャズのような雰囲気もありつつ、独特のローファイさを追求したようなサウンドが心地よいです。フォークやR&Bを想わせる独特のヴォーカルもまた心に染み入るような優しさを感じます。
今作のタイトルでもある「The Heavy Loop」も30分のインプロヴィゼーション・トラックになっており、ノイズやエクスペリメンタルなどの影響も感じ取れる、これまで以上に自由な演奏を披露しています。
次にご紹介するのはまた違ったフィーリングを感じることができるニューエイジ作品。
【CASSETTE】織川一 Hajime Orikawa / 穂遊 Suiyu〈造園計画〉
¥1,999 (税込)
メンバーが入れ替わる不定形のセッション集団、野流の創設メンバーでもあり、千葉県鎌取出身の音楽家、織川一による第一音源集。
ニューエイジの伝説的人物であるLaraajiのライブに衝撃を受け、オートハープを始めたという彼。今作では、オートハープ、エレピ、ムーグシンセ、オルガン、テナーサックスなどの楽器と環境音を宅録で重ね合わせています。
郊外都市のためのニューエイジとも評される独特の空気感が心地よい一枚。やはり日本から生まれた音楽は、どこか日本の土地から感じられるフィーリングの音になっているような気がします。
次にご紹介するのも日本の音楽にフォーカスしたコンピレーションです。
【LP】V.A. / Virtual Dreams II - Ambient Explorations In The House & Techno Age, Japan 1993-1999〈Music From Memory〉
¥6,160 (税込)
【CD】V.A. / Virtual Dreams II - Ambient Explorations In The House & Techno Age, Japan 1993-1999〈Music From Memory〉
¥3,740 (税込)
アンビエント/ニューエイジ最重要レーベル〈Music From Memory〉が手掛けたアンビエントテクノのコンピレーションとして話題となった『Virtual Dreams』の続編。90年代前半のIDM、ベッドルームテクノの影響を受けながらも、独自の発展を続けていた日本国内のシーンから生まれたアンビエント・テクノに焦点を当てて選曲されています。
同レーベルの名コンピ「HEISEI NO OTO」でも選曲を行っていた大阪のレコードショップ REVELATION TIMEの店主、Eiji Taniguchiと、〈Music From Memory〉の創始者であり、2023年末に急逝した稀代の音楽探求家であるJamie Tiller がセレクト。
ほとんどの楽曲がCDでしか聴けなかった希少な音源。個人的には各トラックのサウンドから日本の電子音楽らしさを感じることができて興味深かったです。また当時を知らない自分からすると、このコンピレーションを通じてこういったシーンやアーティストがいたことを知れたということもあり、そういう意味でもおすすめしたい一枚です。
最後にご紹介するのは秋の夜長にぴったりの作品です。
【CASSETTE】Diana Chiaki / Under Control〈Nocturnal Technology〉
¥2,860 (税込)
東京を代表するDJ/プロデューサーのMars89によるレーベル〈Nocturnal Technology〉からのニューリリース。BOLER ROOM、FUJI ROCK等への出演から、CMの楽曲制作まで活躍の幅を広げる、DJ/プロデューサーのDiana Chiakiによるアルバム。
ミニマルでありながら、パワフルなベースラインとビートが効いたスローテクノ。1曲目の「0:00」から最後の「6:00」までで夜明けを表現しているとのことで、どこか夜中から明け方の非現実的な雰囲気も感じます。カセットで聴くのもよさそうです。
ということで、新入荷の商品から4点ご紹介させていただきました!
オンラインショップに載らない店頭のみの商品もありますので、是非ご来店お待ちしております!店頭でレコードなどの試聴もしていただけます。
また、店頭のみの商品もinstagramのDMやお電話でお問い合わせいただければ、通販可能ですので是非お気軽にご連絡くださいませ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。