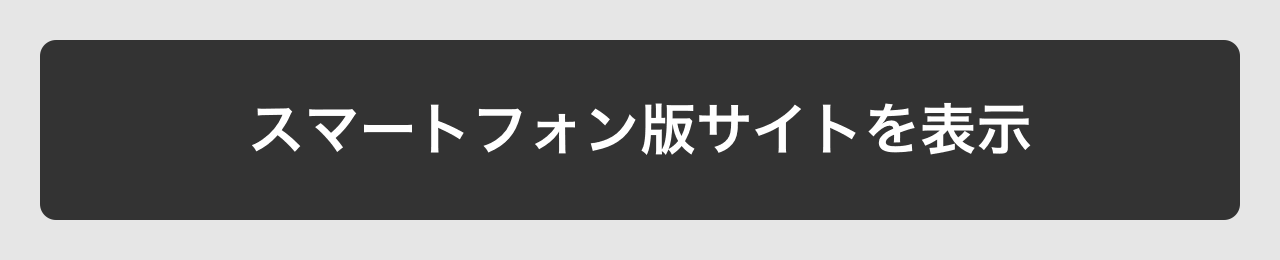こんにちは。BEAMS RECORDSスタッフの和田です!
突然ですが、皆さんは銭湯はお好きでしょうか。私は家から歩いて5分ほどのところに銭湯があるのですが、めんどくさくてあまり行きません。たまに行くと気持ちいいのですが、お湯に浸かったりサウナに入っている時間が退屈に感じてしまう時があり、家のシャワーで済ませてしまうことが多いです。(最寄りの銭湯はサウナに入りながら、イヤホンをしていたり本を読んでいる人が多く、最初は驚きました。)それから、熱すぎるお湯も苦手で、場所によっては一瞬しか入っていられない時もあります。そんな銭湯が得意とはいえない自分が、先日友人の家に遊びに行った際に立ち寄った銭湯が素晴らしく感動しました。
そこは繁華街のはずれでひっそりと営業されている、昔ながらの銭湯。体を洗ってお湯に浸かってみると何かがいつもと違うことに気づきました。普段だったら入ってしばらくは熱くて、慣れるまで時間がかかるのですが、その日は入った瞬間から優しい気持ちよさがありました。なぜかいつもよりお湯が柔らかい感じがすることに気づき、その銭湯に通っている友人にそのことを伝えると、薪でお風呂を沸かしているから、お湯が柔らかくて気持ちいいのだと教えてくれました。
一体それが科学的に証明できる事なのかは自分にはわかりませんが、同じ水道水を使っていても沸かし方の違いで、感じ方がここまで変わるのかと驚きました。さて、銭湯の話が長くなってしまいましたが、これは音楽にも通じる話だと思い、書いてみました。同じ音源を聴いているのにデジタルデータとレコードで音の違いを感じるというのはまさにそうで、アナログなものにはどこか不思議な魅力があり、人はそこに惹かれるのではないのでしょうか。利便性やコスト面でいえばデジタルの方が優れているのに、いまだにフィルムの写真や映像にこだわる作家や、アナログ・シンセサイザーを愛用する音楽家がたくさんいます。
また、当店でお取り扱いさせていただいている〈TAGUCHI〉のスピーカーにも同じような魅力を感じます。元々はコンサートホールや映画館などのために、オーダーメイドのスピーカーを作られていたブランドということもあり、注文が入ってから一つ一つ手作りで作られるスピーカーの音には、どこか暖かみや柔らかさを感じます。高い技術力によって生まれるハイクオリティな音はもちろんのこと、職人の方の手作業によって特別な魅力が宿っているのも、沢山の人々に愛されている理由の一つなのかもしれません。

画像左が〈TAGUCHI〉の スピーカーCANARIO、右がLITTLE BELというモデル。どちらも木目を生かしたデザインが素敵です。
店頭でご視聴もしていただけますので気になる方は是非お越しくださいませ!
話が逸れてしまいましたが、最近はそういったアナログ、オーガニックなものを少しずつ生活の中で増やしていけたら幸せだなと思っています。レコードやカセットテープもその一部ですが、料理を作ったり、コーヒーを淹れたり、植物を育てたりすることにもハマっています。また、最近は生楽器やパーカッションなどが入っていたり、人間らしいグルーヴがあったりと、どこか有機的なエレクトロニックに惹かれることが多いです。
ということで話が長くなってしまいましたが、新入荷のタイトルから個人的にそんな雰囲気を感じるものをご紹介します。

【LP】Contours / Elevations〈Music From Memory〉
まず一つ目は、マンチェスターを拠点にドラマーとしても活動するTom BurfordによるプロジェクトContours(コントゥアーズ)の新作。ニューエイジ/アンビエント系の最重要レーベルでお馴染みの〈Music From Memory〉からリリースされました。マリの木琴のような打楽器であるバラフォンの探求から始まったというこのプロジェクトは、広大な自然の中で自分を忘れたいという彼自身の願望が反映されているそうです。アコースティックとエレクトロニクスそれぞれが調和しており、オーガニックなアンビエント・サウンドを創り上げています。パンデミック期に同世代の音楽家たちと自宅でレコーディングされたということもあり、親密で繊細な印象も感じます。Nala Sinephloなどのアンビエント・ジャズ好きな方に是非聴いていただきたい作品です。

【LP】Mixmaster Morris, Jonah Sharp, Haruomi Hosono / Quiet Logic〈WRWTFWW〉
続いてご紹介するのは、細野晴臣、Mixmaster Morris(ミックスマスター・モリス)、Jonah Sharp(ヨナ・シャープ)の三者によるアンビエント・テクノの名盤。1997年に細野晴臣のスタジオで制作されCDとカセットでのみリリースされたものが、良質な再発を続けるスイスのレーベル〈WRWTFWWR〉から初めてヴァイナル化されました!有機的に変化し続けるドラムパターンと洗練されたシンセサイザーが絡み合うトラックは、今聴いても全く色褪せないサウンドです。この機会に是非LPでどうぞ!
そして、最後に紹介するのはDIY感溢れるデザインのミックスCDになります。

悪魔の沼 with MOOD魔N / 沼探り〈ALLIGATER〉
Compuma、Dr.Nishimura、AwanoからなるDJユニット、悪魔の沼。彼らが”FESTIVAL de FRUE 2022”で、MOODMANを迎えた4人の特別編成で行ったプレイを記録したものがCD化。「沼探り」というタイトル通り、4人が様々なジャンルを横断しながら、ディープな世界観でスローなテクノを展開していく様はまさに抜けられない沼のようです。カオスでスリリングなミックスでありながら、経験に裏打ちされた安定感がやはり素晴らしいです!前半78分間がCDには収録されていて、DLコードから3時間のフルバージョン(MP3)がダウンロード可能となっています。盤に押されたハンドスタンプ、ペーパー・スリーブもDIY感がありかっこいいです!
以上、新入荷の中から3点ご紹介させていただきました!
店頭でしか販売していないアイテムもありますので、是非お近くの際はご来店いただけると幸いです♪♪
最後まで読んでいただきありがとうございました。