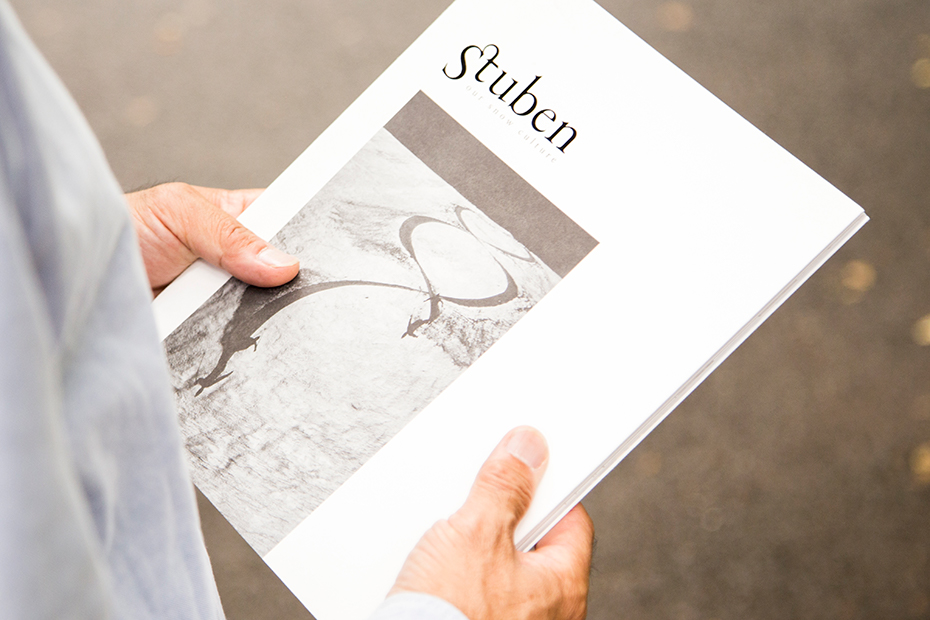14 Yoichi Watanabe Skier/Photographer
Text : Lisa Obinata 2012年冬にBギャラリーで写真展を行なった北海道ニセコ在住、写真家でスキーヤーの渡辺洋一氏とBギャラリー キュレーター藤木洋介によるトーク。90年代より国内外での様々な活動を通し、スキーをはじめとした雪山での暮らしを伝え続けてきた彼も今年で50歳を迎え、また新たなるチャレンジに向かっています。そんな渡辺氏のこれまでの活動から、表現の一つとして昨年より編集者、尾日向梨沙と立ち上げたスノーカルチャーマガジン「Stuben Magazine(スチューベン・マガジン)」についても伺いました。
自然の雪山を滑る
- Yosuke Fujiki (以下、Y.F) :
- 渡辺洋一さんはニセコにお住まいですが、幼少期は関東で過ごされたんですよね? 長く続けているスキーの経緯を簡単に教えていただけますか。
- Yoichi Watanabe (以下、Y.W) :
- 子供の頃は立川や所沢に住んでいました。スキーを始めたのは小学校3年生の時。新潟県の六日町に行ったんですが、スキーは転んでばかりで全然おもしろいと思わなかったんですね。どちらかというと、一面真っ白の雪景色が強く印象的に残りました。中学生からはタイムを競う競技スキーを始めて、社会人になるまで続けていました。
- Y.F
- 今は自然の雪山を滑るというイメージですが、そのキッカケは?
- Y.W
- 高校生の頃、合宿で富山県の立山に行ったんですが、その時パウダースノーを滑ってふかふかで感激したんですよ。それから20代前半の春、山スキーに出会い、整地されたコースではなく、大自然の中で滑るおもしろさを知りました。
もともと都会育ちではなく、所沢の自然豊かなところで育ったので、自然の中で遊ぶことが好きで、そこがベースとなっているんでしょうね。26歳の頃、スキーがしたくて会社に転勤の希望を出して、札幌に転勤。この頃は北海道のあちこちの山を滑っていましたね。ニセコに移住して、50歳になった今までスキー一筋の暮らしを送っています。
- Y.F
- 僕が初めてニセコに行った時、スキーはほとんどしたことがなかったんですが、洋一さんに全部道具を借りて教わって。最後にコース脇の森に行こうと言われ、その時いろんな体験をさせてもらったんですよね。その中でも「スキーは自由の翼だ」という洋一さんの言葉が印象的で。夏は笹薮の壁で入れないところも、雪が積もると自然と道ができて、スキーを履けばどこにでも進んで行けるんだということを学びました。この体験はスキーに対する僕のイメージを大きく変えた出来事でした。
- Y.W
- そうですね。スキー場の中ってリフトに乗って、コースも決まってるから、遊園地の中で遊んでるようなもの。山の中は、自分たちが子供の時に雑木林で遊んだように自由。海でサーフィンするのと同じで、ただの雪山はどこでも滑れる。そういう精神的にも自由を感じられる部分が楽しいですよね。
スキーとファッション
- Y.F
- スキーウェアの変化って、どんな感じなんですか?
- Y.W
- 1800年後半や1900年前半のスキー写真や映画を見ていると、ニットセーターに、ニッカボッカを履き、ツイードのジャケットを着るなどお洒落なんですね。日本にスキーが入ってきた戦前のスキーヤーもクラシックな装いをしていたし、スキー板も無垢の木を削り出して作っていたんです。自然にある物や素材を用い、自然の中で遊び、旅する道具でした。スキーがオリンピック競技になり、より速く滑るためにさまざまな素材開発が進むと、コマーシャル性が高くなっていった気がします。スキーは本来、自然を感じる行為として存在するはずなのに、スキー場がどんどんできて、都会からの集客を募るために、都会の人向けに遊び場も着る服も変わっていきました。とくに1980年代~1990年代は、誰よりも目立つようカラフルになり、会社の名前やスポンサーの名前が目立つ派手なウェアが多くなっていきましたね。
- Y.F
- 洋一さんはいつもアウトドアブランドのウェアで滑っていますよね?
- Y.W
- そうですね。自然の中を滑る山スキーが、アメリカなどで「エクストリームスキー」と呼ばれ、1990年代始めからムービーや雑誌などで日本に紹介されたんです。その頃からスキーウェアメーカー製ではなく、<THE NORTH FACE>、<patagonia>、<Marmot>などのいわゆるアウトドアウェアメーカーのマウンテンパーカーを着て滑る人が出始めました。テレマークスキーヤーは1980年代から<patagonia>などを着て滑っていたんですよ。僕が最初にアウトドアウェアで滑ったのも北海道に移住した26歳の時で、<Marmot>のジャケットに<patagonia>のナイトロパンツ。その頃、ニセコではパウダーを滑るのに歩き、登る必要から、ローカルはアウトドアメーカーを選んでいました。
- Y.F
- 今はどうですか?
- Y.W
- 日本国内のスキー事情もメディアなどを通じて、パウダースノーを滑るようなアウトドアスポーツ色が広まり、使用する道具もずいぶん変わりましたね。その影響力がどんどん大きくなり、競技やイベント向けの色が強い日本のスキーウェアメーカーの服もシンプルなデザインになってきました。今では<GOLDWIN>や<DESCENTE>がメインラインナップで極めてシンプルなデザインのスキーウェアを展開しています。自然の中で活動するのに見合うデザインと、高い機能の服を着て滑ることは普通になったという感覚です。
写真と「Stuben Magazine」
- Y.F
- 2012年には、ニセコの森を撮りおろした、写真展「白い森」をBギャラリーで開催していただきました。そもそも写真との出会いやキッカケは?
- Y.W
- もともと家系に研究者や教師、写真を趣味としている人がいました。弟はファッションのフォトグラファーで家にはカメラがたくさんありました。子供の頃から雑誌もよく買っていたし、レコードはジャケ買いをしたりなど、写真に興味があったんですね。
それでコンパクトカメラを買って、山に行く時も構図を考えて撮っていました。ある時、撮った写真を一緒にいた友達にプリントしてあげたらすごい喜んでくれて。写真の仕事できるんじゃないかなって思いました。ちょうどサラリーマンをやめてニセコに移り住み、仕事をせずスキーばかりしていた頃だったので、スキーの写真を撮るのは自分に合っている感覚がありましたね。
- Y.F
- 洋一さんはスキーを滑るだけでなく、ガイドをしたり映像作品や写真集を作ったり、写真展を開くなど精力的に活動をされています。そして昨年にはスノーカルチャーマガジンの創刊まで。ビームスはその文化的な活動に共感し応援しているのですが、なぜスキーを滑るだけでなく、スキーをカルチャーとして伝えるということにこだわっているのですか?
- Y.W
- なんでですかねぇ。多分、「伝えたい」という部分が強いんでしょうね。子供の頃から決まった道やレールを歩むのはあまり得意ではありませんでした。結局大学に進学し、名前がある会社に入って、お給料もらって、という時代を通ったんですが、ある時、スーツを着ている自分を鏡で見て「何か違う」と思ったんです。このまま決められた道を歩む人生はどうなんだろう、と。自分らしい発想や感性でモノ作りがしたい、というのが根底にありますね。
スキーや雪国の暮らしも、過去の歴史に触れ、先人の言葉や哲学に耳を傾けると、どうやらスキーヤーとしての生き方があり、自分はそれを探しているんですよ。冬の雪から自然を深く知ることを伝えたいんです。その表現のひとつが、今回の「Stuben Magazine」だと思います。
- Y.F
- 北海道ニセコに暮らしているからこそ、思い浮かぶアイデアを形にしているという印象を受けます。僕も何度かニセコに伺いましたが、自然が教えてくれることってたくさんありますよね。
- Y.W
- 日本って実はすごく自然に恵まれている島国なんです。東京からなら2時間で雪山に行けてスキーできるし、1時間で海でサーフィンできる。そしてこれだけの経済大国。もっと自然を使ったもので楽しむ人生を提案したいですね。その冬版を自分が担当しているつもりでいます。自然の中で遊んだり暮らすことはとても重要で、穏やかな精神が保て、人々にも優しくなれますよね。
僕の暮らすニセコは、山岳地だけれど意外と日本海も近いんです。海が近いということは、雪が多いということ。海の養分をたっぷり吸った雪が積もり、春になると融けて、海の養分が森や畑に浸透していく。私たちはその作物を食べています。また雪融け水は川をつたい、海に流れていく。こういった自然の循環の中に暮らしているということを感じやすい。なので身近にある自然環境について考えることも、ごく普通のことなんですよね。
-
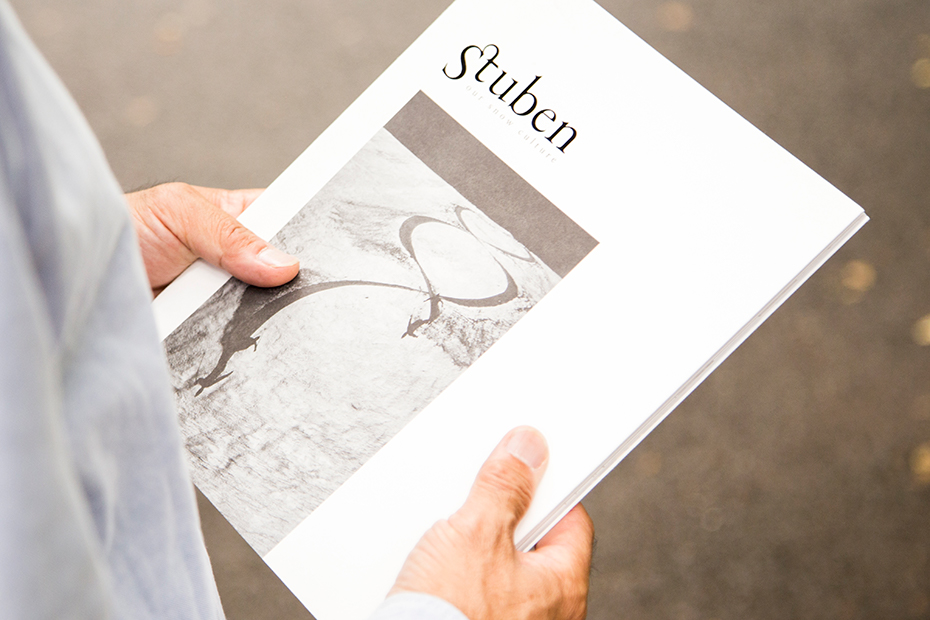
「Stuben Magazine」
2015年創刊の「Stuben Magazine」は渡辺洋一氏がクリエイティブディレクターを務めるスノーカルチャー誌。2016年10月18日に第2号目が発売。BEAMSの一部店舗とオンラインストアでも販売する。詳しくはこちら。 -

<SMITH>ゴーグル
ディープパウダースノーが日常のニセコでは、滑走時に頭の上まで雪が巻き上がることもある。そんな状況でもクリアな視界を確保できる<SMITH>ゴーグルは必需品。
-

<OSPREY>のバッグ
<OSPREY>は早くから背面が開くバックパックを作っていて、雪上でのカメラバッグとしても長く愛用しているという氏。街でも使えるキャリーバッグは出張時に便利。 -

<LEICA>
「レンズ特性からの描写力と手に収まる機動性が良いボディサイズが気に入っています。<LEICA>はスキー写真の歴史上も重要なメーカーなので、ストーリー性も大事に思っています」という最近愛用のカメラ。
- Y.F
- 「Stuben Magazine」第2号では、環境について特集すると聞きましたが、内容について教えてもらえますか?
- Y.W
- 自然に感謝とかそういう話ではなくて、おいしい水や野菜を摂りたいし、これからもいい雪を滑って、自然の中で豊かに暮らしたいというシンプルな思いがあります。
僕らが何かやったくらいで、地球の自然環境はそう簡単には変えられないけど、できることを考え、簡単なことでも取り組んでいったほうがいいだろうと。
今号では、山岳リゾートと自然エネルギーについて記事を書きました。何年も前から、ヨーロッパへ取材に行くたびに自然エネルギーで地域が成り立っていることを知って、興味をもって取材をし続けたんです。
自分と同じように田舎の村や町で生活をしている人たちのところで勉強して、写真に撮り、まとめました。国内の事例も紹介するので、これなら自分にもできると、気付いてもらえたらいいですね。
- Y.F
- それは楽しみですね。スキーヤー、写真家としての活動に留まらない渡辺洋一という一人の人間、そしてその人間の中の一表現としての「Stuben Magazine」の動向に、これからも注目し続けていきたいと思います。どうもありがとうございました。

(Skier/Photographer)
1966年生まれ、北海道ニセコ高原在住。ウパシ プロダクション主宰。スキーヤーとして雪国に暮らし、雪を求め世界を旅して写真を制作。1990年代よりニセコの人々とパウダースノーを写真に収め、映像作品「ruwe」シリーズ、写真集「NISEKO POWDER」、専門誌や広告に発表。同時に国内外のスキーシーンを撮影し写真集「雪山を滑る人」を発表。国内外の数々のアウトドアアパレルの撮影も手がけている。近年は写真展「白い森」「後方羊蹄山を滑る」、写真集「BROAD LEAF SNOW TREE」など地元ニセコを題材にした作品を発表する。スキー史や雪国の風土をテーマに、独自の表現で発信を続ける。http://yoichiwatanabe.jp/

(B GALLERY Curator)
1978年生まれ。BEAMSが運営するBギャラリーのキュレーターとして展覧会の企画から運営を手掛ける傍ら、ギャラリーや美術館への企画持ち込み、国内外のアートフェア出展なども積極的に行っている。その他、福永一夫 写真集『美術家 森村泰昌の舞台裏(発行:ビームス/2012)』企画、操上和美 写真集『SELF PORTRAIT(発行:ビームス/2015)』企画・編集など。http://www.beams.co.jp/bgallery/